目次
社会福祉協議会(自治体)の緊急小口資金でお金を借りる方法とは

日本全国の47都道府県には、社会福祉協議会が必ず存在します。そして、緊急小口資金とは社会福祉協議会が、低所得世帯が一定の理由により緊急かつ一時的に生活ができなくなった場合に、少額の貸付を行う制度のことです。
そもそも、社会福祉協議会とは?

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動の推進を目的とした公的組織のことです。全国・各都道府県・各市町村で組織されています。民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育分野などの関係機関が参加・協力し、以下の活動を行っていると考えましょう。
- 住民の地域福祉活動に対する支援
- ボランティア・市民活動の推進・支援
- 地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供や連絡調整
- 経済的な支援を必要とする人に対する生活福祉資金等の貸付
- 日常生活自立支援事業(高齢や障害等により判断能力に不安のある人を対象とした福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行う事業)
- 介護サービスなどの多様な在宅福祉サービスの提供

緊急小口資金とは?


緊急小口資金とは、低所得世帯が次のような理由で緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に少額の貸し付けを行う制度です。
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
- 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
緊急小口資金を利用できるのはどんな人?

イメージとしては「住民税が非課税になる世帯」と考えましょう。例えば、東京都の場合、以下の条件にあてはまれば住民税が非課税になります。
- これまで定期的な収入により生計を維持してきた
- 世帯の収入が所定の収入基準を超えていない

| 世帯人員 | 平均月収 |
|---|---|
| 1人 | 191,000円 |
| 2人 | 272,000円 |
| 3人 | 335,000円 |
| 4人 | 385,000円 |
| 5人 | 425,000円 |
なお、低所得世帯であることだけでは、緊急小口資金の制度は利用できません。次の2つの要件を満たす必要があります。
- 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況である
- 返済(償還)の見通しが立つ
貸付内容及び条件はどうなっている?
具体的な貸付内容および条件は、都道府県や市区町村ごとに若干異なります。ここでは東京都の場合の貸付内容と条件を紹介しましょう。
| 貸付限度額 | 10万円以内(1,000円単位) |
|---|---|
| 貸付利子 | 無利子 |
| 据置期間 | 2カ月 |
| 返済期間 | 12カ月以内 |
| 返済方法 | 原則として口座引落で月賦返済 |
| 連帯保証人 | 不要 |
なお、5万円を超える貸付を必要とする場合は、配偶者等も社会福祉協議会での面接が必要になります。

社会福祉協議会(自治体)の緊急小口資金でお金を借りる方法のメリット
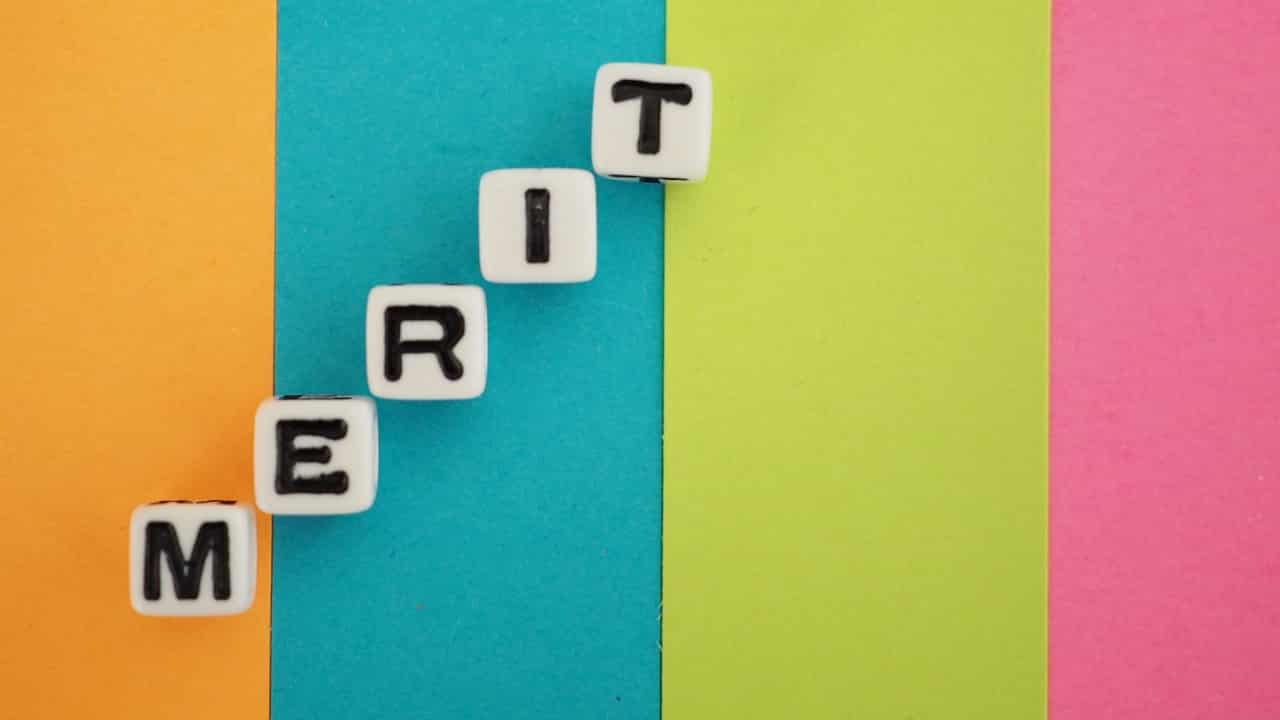
ここで、社会福祉協議会の緊急小口資金でお金を借りる方法のメリットとして
- 無利子で利用でき、連帯保証人も不要である
ことについて解説しましょう。
1.無利子で利用でき、連帯保証人も不要である
緊急小口資金の利用にあたっては、利子はかかりません。連帯保証人を立てる必要もないので、周囲にお金を借りるのを知られることもありえません。
実際に連帯保証人をたてようとしたら、誰になら頼めそうかを考えなくてはいけません。また、頼めそうな人がいたとしても快諾してもらえるとは限りません。話の進め方によっては、トラブルの原因にもなるので、スピーディーに手続きを進めるためにも、連帯保証人がいらないというのはメリットになりえます。
社会福祉協議会(自治体)の緊急小口資金でお金を借りる方法のデメリット

一方、緊急小口資金でお金を借りる方法のデメリットについて
- 利用目的がかなり限定されている
- その日に借りることはまずできない
- 多額の借り入れはできない
- 収入基準が意外と厳しい
の4点から解説しましょう。
1.利用目的がかなり限定されている
緊急小口資金は、あくまで「一時的に生活費が不足している分を貸し付けて、生活を立て直し、自立するために貸し出すもの」として位置づけられています。そのため、貸し付けを受けた資金の利用目的は、かなり限定されていることに注意が必要です。
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
- 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
また、これらの目的以外での資金の利用が認められない以上、以下の条件に当てはまる場合は利用できないことにも注意が必要です。
- 生活保護世帯
- 収入がないかまたは少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯
- 多額な負債があるまたは返済が滞っている人がいる世帯
- 債務整理の予定があるまたは債務整理中の人がいる世帯
- 生活状況が確認できない世帯

2.その日のうちに借りることはまずできない
緊急小口資金は、各自治体と社会福祉協議会が合同で運営する公的な制度です。制度の趣旨を踏まえ、本当に必要な人が適切に利用できるようにするため、審査は時間をかけてじっくり行われます。
3.多額の借り入れはできない
この制度の趣旨は、あくまで「一時的な生活費の不足に対応する」ことです。そのため、必要最低限の金額しか借り入れができません。「ある程度はまとまったお金を確保しておきたい」という人にとっては、あまり魅力的な制度ではないのも事実です。

4.収入基準が意外と厳しい
緊急小口資金は「本当にお金に困っている人」のための制度でもあるため、厳しい収入基準が設けられています。
東京都の場合、2019年度の収入基準は以下の通りです。つまり、1年間の平均月収がこの表の水準を下回るかどうかで制度を利用できるかどうかが決まります。
| 世帯人員 | 平均月収 |
|---|---|
| 1人 | 191,000円 |
| 2人 | 272,000円 |
| 3人 | 335,000円 |
| 4人 | 385,000円 |
| 5人 | 425,000円 |
問題なのは、この表に記載された平均月収をちょっとだけ上回っているケースでしょう。緊急小口資金は利用できないのに、決して生活に余裕があるわけではない、という人も出てくるということです。

社会福祉協議会(自治体)の緊急小口資金でお金を借りるまでの手順

実際に、社会福祉協議会の緊急小口資金でお金を借りる場合、どのような手順で進んでいくのかを知っておきましょう。大まかな流れは以下の通りです。
- 最寄りの社会福祉協議会に連絡し、相談する
- 必要な書類を揃える
- 申し込みをし、審査を受ける
- 貸付が決定したら融資が実行される
- あらかじめ定められた返済スケジュールに従い返済していく
それぞれのステップについて、もっと細かく解説しましょう。
1.最寄りの社会福祉協議会に連絡し、相談する
利用を検討する際は、まずは最寄りの社会福祉協議会に連絡し、相談しましょう。緊急小口資金はあくまで「世帯への貸付」という考え方をとっています。そのため、自分についてはもちろんのこと、家族の状況・収入・負債など幅広い事柄に対し、担当者によるヒアリングが行われるのが大きな特徴です。
また、これらのヒアリングの際に、さらに詳しく状況を確認するため、書類の提示を求められるケースもあります。相談し、指示があった書類については、すぐに提出できるように用意しておきましょう。
2.必要な書類を揃える
担当者とのヒアリングを終え、緊急小口資金を利用することを決めた場合は、必要な書類を用意しましょう。東京都の場合、以下の書類を提出するよう求められます。
| 借入申込書 | 相談窓口で入手可能 |
|---|---|
| 住民票の写し | 世帯全員分、発行から3カ月以内のもの |
| 健康保険証または顔写真付きの本人確認書類 | 運転免許証、パスポート等 |
| 借入申込者の世帯の収入証明 | 源泉徴収票の写しや確定申告書の写しなど。生計中心者およびその配偶者、世帯の生計維持に寄与している人の分が必要 |
| 借用書 | 相談窓口で入手可能。社会福祉協議会の窓口で、本人による署名をしなくてはいけない |
| 預金口座振替依頼書 | 相談窓口で入手可能。記入にあたっては、通帳と銀行員も用意すること |
| 借入理由による確認書類 | 状況により異なるので詳しくは窓口で確認すること |


| 医療費の支払いにより臨時の生活費が必要なとき | 医療費の領収書(1カ月以内のもの)など |
|---|---|
| 年金の支給開始までに生活費が必要なとき | 年金事務所発行の給付開始日と給付額が確認できる書類など |
| 雇用保証給付制限期間中に生活費が必要な時 | 雇用保険受給資格者証、認定スケジュールなど |
| 公的職業訓練手当開始までに生活費が必要な時 | 就職支援計画書(写)など |
| 初回給与支給までの生活費が必要な時 | 雇用証明書など ※社会福祉協議会から勤務先への電話などによる在籍確認を行うケースもある |

3.申し込みをし、審査を受ける
必要な書類が揃ったら、審査を受けましょう。東京都の場合、まず市区町村の社会福祉協議会に提出し、その後、東京都社会福祉協議会に提出される流れです。また、状況に応じて、電話での確認があったり、追加で書類の提出を求められたりすることもあるので、連絡はつくようにしておきましょう。

4.貸付が決定したら融資が実行される
審査を通過したら、融資が実行されます。東京都の場合、決定した日の翌営業日に本人名義の口座に資金が振り込まれるスケジュールです。実際のスケジュールは、管轄する社会福祉協議会によって異なるので、事前に確認しましょう。
5.あらかじめ定められた返済スケジュールに従い返済していく
借り入れたあとは、あらかじめ定められた返済スケジュールにしたがい返済していきましょう。緊急小口資金には「据置期間」が設けられています。これは、返済を猶予してくれる期間のことです。
例えば、据置期間が2カ月だった場合は、借り入れた月の翌月と翌々月は返済しなくて構いません。3カ月目から返済が始まると考えましょう。

借入をした分の返済がすべて終わると、申し込みにあたって提出した借用書が返却されます。
社会福祉協議会(自治体)の緊急小口資金でお金を借りる際の注意点
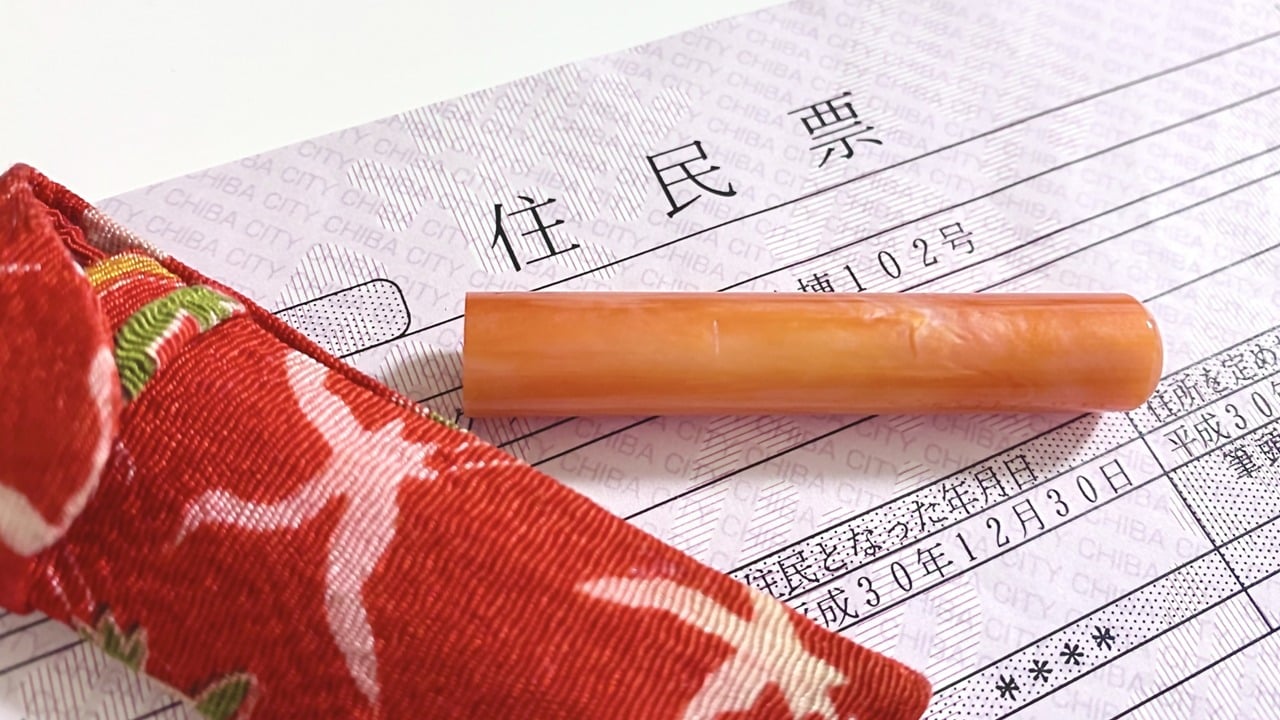
最後に、緊急小口資金を使ってお金を借りる際の注意点についても解説しておきましょう。
1.「貸付が支援になる」と判断されないと使えない
緊急小口資金は、一度に借りられる金額こそ小さいものの、借入=借金です。あとで返済できる見込みがちゃんとあるなら、一時しのぎとしてお金を借りることは決して悪いことはありません。しかし、返済できる見込みもないのに貸してしまっては、かえって負担が増えてその後の生活が立ち行かなくなってしまいます。
この点も勘案して、厳格な運用が行われているのが緊急小口資金の特徴の1つです。担当者とのヒアリングや提出書類の審査を行った結果「負担が大きく、貸し付けすることが適切な支援ではない」と判断されたら、この制度は使えないことに注意しましょう。
2.嘘をつくのは厳禁
緊急小口制度は、いわば税金で運営されている公的な制度です。そのため「本当に必要としている人が利用できること」が非常に重視されています。その目的を達成するためにも、社会福祉協議会の担当者とのやりとりにおいて、嘘はついてはいけません。

3.慢性的に生活に困窮しているなら他の制度の利用も検討しよう
あくまで、緊急小口制度は「一時的に足りないお金をどうにかする」ための制度です。そのため、慢性的にお金に困っている人が利用できる制度とは言えません。
もし、慢性的にお金に困っているなら、生活保護などの他の制度の利用も検討してみましょう。社会福祉協議会に相談してもいいですし、地域の弁護士会や司法書士会、市区町村議会の議員などに相談するのも手段の1つです。




