本ページはプロモーションが含まれています。
目次 非表示
- 「株式投資」おすすめ証券会社比較。ここがポイント!
- 「株式投資」で証券会社の選び方
- 「株式投資」で証券会社の選び時のよくある質問
- 「株式投資」でおすすめの証券会社ランキング/編集部
- 「株式投資」おすすめ証券会社比較
- 「株式投資」でおすすめの証券会社ランキング/利用した方の口コミ・評判
- SBI証券/株式投資の評判・口コミ
- 楽天証券/株式投資の評判・口コミ
- 松井証券/株式投資の評判・口コミ
- マネックス証券/株式投資の評判・口コミ
- SBIネオトレード証券/株式投資の評判・口コミ
- auカブコム証券/株式投資の評判・口コミ
- LINE証券/株式投資の評判・口コミ
- GMOクリック証券/株式投資の評判・口コミ
「株式投資」おすすめ証券会社比較。ここがポイント!
| 運営会社 | SBI証券 | 楽天証券 | LINE証券 | auカブコム証券 | マネックス証券 | 松井証券 | 岡三オンライン | DMM.com証券 | GMOクリック証券 | SBIネオトレード証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開設口座数 | 約7,717,000口座 ※2021年9月末(SBIネオモバイル証券,SBIネオトレード証券含む) | 6,243,338口座 ※2021年6月末 | 約100万口座 ※2021年10月時点 | 1,354,125口座 ※2021年11月時点 | 1,708,735口座 ※2021年12月末 | 1,401,205口座 ※2021年12月末 | 289,660口座 ※2021年11月末 | 非公開 | 481,831口座 ※2022年1月末 | 非公開 |
「株式投資」で証券会社の選び方
1.投資商品で選ぶ
証券会社の提供している投資商品は幅広いものがあります。
- 国内株式
- 外国株式
- 米国株式
- 投資信託
- NISA
- つみたてNISA
- IPO
- CFD(金・原油・先物)
- 債権
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 外国為替証拠金取引(FX)
- オプション取引
- 保険
などなど商品は多岐にわたります。
株式投資だけに限定したとしても、大きく分ければ
- 国内株式
- 米国株式
- 外国株式
- 投資信託
- NISA
- つみたてNISA
- IPO
に別れるのです。
- 国内株式投資をするなら、国内株式投資に強い証券会社
- 米国株式投資をするなら、米国株式投資に強い証券会社
- 投資信託をするなら、投資信託に強い証券会社
- IPO投資をするなら、IPO投資に強い証券会社
- どの取引方法がベストか決められないなら、総合的に取扱いのある証券会社
- 複数の取引方法を併用するなら、総合的に取扱いのある証券会社
という形で
投資すべき投資商品によって、選ぶべき証券会社も変わってくるのです。
「〇〇に強い」証券会社を選ぶポイントは
- 投資商品「〇〇」の取扱いの有無
- 投資商品「〇〇」の取扱商品数の多さ
- 投資商品「〇〇」での市場シェア(利用している投資家の多さ・口座数の多さ)
- 投資商品「〇〇」の手数料の安さ
- 投資商品「〇〇」の情報の安さ
でわかります。
米国株取引に強い証券会社を選ぶとするならば
- 投資商品「米国株」の取扱いの有無
- 投資商品「米国株」の取扱商品数の多さ
- 投資商品「米国株」での市場シェア(利用している投資家の多さ・口座数の多さ)
- 投資商品「米国株」の手数料の安さ
- 投資商品「米国株」の情報の安さ
で決まるということです。
自分が投資したい投資商品に合わせて、そのジャンルに強みのある証券会社を見つけてトレードすることをおすすめします。
2.投資スタイルで選ぶ
株式投資では、様々な投資スタイルがあります。
デイトレードなどの短期売買の投資家
- 取引手数料が安い
- 定額で取引手数料が無料
- 取引ツールの分析機能が充実している
- 使いやすい
長期保有の投資家
- スクリーニング機能が充実している
- 銘柄の情報やニュース、企業分析、分析レポートが充実している
- 銘柄数、取引方法が豊富
少額資金の投資家
- 単元未満株(ミニ株)に投資できる
- NISA、積立NISAに対応している
- キャンペーンが手厚い
大口資金の投資家
- 安全性の高い(倒産リスクの低い)証券会社を選ぶ
IPO狙いの投資家
- IPOの取扱い実績が豊富
- 公平な抽選がある
株主優待狙いの投資家
- 株主優待の情報が豊富
- 株主優待に関するセミナーやイベントがある
初心者投資家
- 単元未満株(ミニ株)に投資できる
- NISA、積立NISAに対応している
- スマホで簡単に取引できる
- キャンペーンが手厚い
- セミナーや動画などの初心者向けコンテンツが多い
- 銘柄数、取引方法が厳選されている
あなたの投資スタイルによって、選ぶべき証券会社というのは変わってくるのです。
「ご自身の投資スタイルで必要な機能やスペックは何なのか?」を明確に定義して、比較要素に優先順位をつけることで、自分にあった証券会社が見つかります。
3.情報コンテンツ・取引ツール・分析ツールで選ぶ
株式投資で重要になるのは「ツール・情報コンテンツ」といっても過言ではありません。
とくに株式投資では
- 企業分析
- スクリーニング(絞込)
- アナリストレポート
などが重要になるツール・情報コンテンツと言えます。
使いたいツール、必要な機能を兼ね備えたツール、必要な情報を提供してくれる証券会社を選ぶことで、株式投資の成功率が引きあがるのです。
「株式投資」で証券会社の選び時のよくある質問
Q.証券会社を選ぶ際に「手数料の安さ」と「サービスの良さ」はどちらが重要ですか?
「サービスの良さ」には色々あり、投資スタイルにもよりますが
- 取引ツール
- 分析ツール
- アナリストレポート
などが充実している証券会社を選ぶ方が、長い目で見たときにお得である可能性が高いです。
短期的な売買、一過性のキャンペーンでのプレゼントなどに重きを置くのであれば、特典や手数料無料というのが大きなお得になります。
しかしながら、数年単位で「取引のスキルを磨いて、大きく稼げるようになる」ことを目的とするのであれば、多くの証券会社を併用し、高度な取引ツール、高度な情報コンテンツを獲得して、トレードしていった方が、長い目で見た場合に、稼げる可能性が高いと考えます。

「短期的に安い、お得だから良い証券会社」というわけではなく、「長期的に自分の投資スキルが上がる証券会社を選ぶ」ということも重要と考えます。
「株式投資」でおすすめの証券会社ランキング/編集部

SBI証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 5
-
- 手数料の安さ
- 5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 5
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 4
-
- サービスの利便性
- 4
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | SBI証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■スタンダードプラン ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■アクティブプラン ~100万円:0円 ~200万円:1,238円 ~300万円:1,691円 以降100万円ごとに:295円 |
| 開設口座数 | 約7,717,000口座 ※2021年9月末(SBIネオモバイル証券,SBIネオトレード証券含む) |
| IPO実績(直近年間) | 85社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・オプション ・CFD(くりっく株365) ・金・銀・プラチナ ・eワラント ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・保険 |
| 外国株 | 米国株式、インドネシア株式、中国株式、シンガポール株式、韓国株式、タイ株式、ロシア株式、マレーシア株式、ベトナム株式 |
| 米国株(銘柄数) | 302銘柄 |
| 投資信託数 | 2,650銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 174銘柄 |
| 取引ツール | ・HYPER SBI ・SBI CFDトレーダー |
| アプリ | ・SBI証券 株アプリ ・SBI証券 米国株アプリ ・かんたん積立 アプリ ・HYPER FXアプリ ・HYPER 先物/オプションアプリ ・HYPER CFDアプリ |
| ポイント投資 | Tポイント、Pontaポイント |
| ポイント付与 | Tポイント、Pontaポイント、Vポイント |
| クレジットカード積立投信 | ○ |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
SBI証券/株式投資がおすすめの理由
SBI証券/株式投資がおすすめの理由は「手数料の安さ」「取引商品の多さ」です。
SBI証券では、アクティブプランであれば「100万円までは取引手数料無料」でトレードをすることができます。また、株式投資・投資信託・債権・オプション・先物商品・iDeCO・NISAといった幅広い投資商品があり、外国株も、300銘柄以上を取り扱うなど、幅広い選択肢が用意されている点が魅力の証券会社です。
また、アプリも充実しており、クレジットカードでの積立投信も可能、ポイント投資も可能と、利便性も高く多くの投資家に重宝されている証券会社です。
デメリットは、デモ口座がない点と日本株と米国株の取引ツールが別になってしまう点です。
SBI証券/株式投資の口コミ

楽天証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 5
-
- 手数料の安さ
- 5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 5
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 5
-
- サービスの利便性
- 4
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | 楽天証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■超割コース ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■いちにち定額コース ~100万円:0円 ~200万円:2,200円 ~300万円:3,300円 300万円~:以降100万円ごとに1,100円 |
| 開設口座数 | 6,243,338口座 ※2021年6月末 |
| IPO実績(直近年間) | 38社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・バイナリーオプション ・FX ・CFD ・金・銀・プラチナ ・eワラント ・iDeCo(個人型確定拠出年金) |
| 外国株 | 米国株式、インドネシア株式、中国株式、シンガポール株式、タイ株式、マレーシア株式 |
| 米国株(銘柄数) | 4,484銘柄 |
| 投資信託数 | 2,664銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 179銘柄 |
| 取引ツール | ・マーケットスピード2 ・マーケットスピード ・マーケットスピード for Mac ・マーケットスピード II RSS ・マーケットスピードFX ・楽天MT4 |
| アプリ | ・iSPEED ・iSPEED for iPad ・iSPEED FX ・iSPEED 先物 |
| ポイント投資 | 楽天スーパーポイント |
| ポイント付与 | 楽天スーパーポイント |
| クレジットカード積立投信 | ○ |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
楽天証券/株式投資がおすすめの理由
楽天証券/株式投資がおすすめの理由は「楽天ポイントが使える」点です。
楽天ポイントは、楽天カードや楽天市場での買い物で貯まりやすいポイントで、そのポイントをそのまま投資に利用できるポイント投資が可能になるため、楽天経済圏を使い倒す投資家にとっては、かなりお得に利用ができる証券会社と言えます。
証券会社としても、取引手数料が安く、米国株やNISA、iDeCoに対応するなど、初心者にも使いやすいサービスを提供しています。
デメリットは、IPO実績が少ない点とミニ株投資ができない点です。
楽天証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:125件
複数の証券会社を利用していますが、楽天証券のインターフェースが一番見やすくて使いやすいです。四季報も無料で読めたりと便利に使えます。最近の楽天全体の改悪によって投資信託を保有していることに対して付与されていたポイントが大幅に減ってしまったのは残念ですが、楽天カードと楽天キャッシュをあわせて10万円までキャッシュレス決済で投資信託を積み立てられるのはやはりメリットが大きいと思います。楽天銀行と併用すると普通預金でも0.1%の金利が得られることもよいと思います。
楽天証券で株式投資をしています。普段利用する商品をもらったりサービスの割引をしてくれる株主優待目当てで株を買いました。私は何かとズボラな性格で一度株を買うと何ヶ月もサイトを開かず放っておくことが多いです。楽天証券は決算発表のメールを送ってくれてわかるようになっているのがありがたいです。また楽天銀行との連携サービスであるマネーブリッジを利用しており楽天銀行から出入金時の手数料が無料になる、ポイントがたまるなどのサービスが充実しています。
投資歴は5年前に楽天証券ではない普段使いの労働金庫でのつみたてNISAを始め、一年少し前から楽天証券で全米インデックス連動の投資信託(楽天VTI)や、日本の高配当個別株、アメリカの高配当ETFへの投資を始めました。正直、店舗型よりもネット証券である楽天証券の方が各種手数料が安いことや、楽天経済圏どっぷりの生活を送っていることから、楽天証券での投資が様々なコスト、ポイントによる生活費の削減という観点から優れています。コロナ禍で始めた投資なので、その後の景気回復を受けどこの証券会社でも含み益は大きくなっていると思いますし、SBIなど手数料も安くポイントも改善される中、ポイント改悪の続く楽天ですが、国内大手経済圏の楽天の持つアドバンテージはまだまだ大きいと感じます。
まず手数料が安いです。一日100万円まで無料なので手数料がかかることが殆どありません。
マネーブリッジに登録すると楽天銀行から証券口座に随時に自動送金、自動返金されるので口座残高を気にせず済むのが便利に感じています。手数料もかかりません。
取引で楽天ポイントがそこそこ貯まること、貯まったポイントが使えるのも嬉しいです。最近ルールが改悪されてポイント還元率が下がったことと、期間限定ポイントは相変わらず使えないことは不満ですが。
楽天証券を使用しておりますが、口座開設までの流れ・手順が簡単でマイナンバーカードがあれば数日で証券口座を開設出来ました。スマホアプリで取引・管理が出来て、相場の動きも手軽に見れるので使いやすいです。また、アプリ内の検索フォームが充実していて自分が調べたい銘柄も色んな方法で検索出来ます。その他にも楽天市場などで溜まった楽天ポイントも購入時に使用可能なので普段から楽天を使っている方にはより便利だと思います。

LINE証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 4
-
- 手数料の安さ
- 4
-
- 取扱銘柄の多さ
- 3
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 4
-
- サービスの利便性
- 3
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | LINE証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■超割コース ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | – |
| 開設口座数 | 約100万口座 ※2021年10月時点 |
| IPO実績(直近年間) | 11社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・投資信託 ・iDeCo(個人型確定拠出年金) |
| 外国株 | – |
| 米国株(銘柄数) | – |
| 投資信託数 | 32銘柄 |
| NISA | – |
| 積立NISA(銘柄数) | – |
| 取引ツール | ・LINE |
| アプリ | ・LINE |
| ポイント投資 | LINEポイント |
| ポイント付与 | – |
| クレジットカード積立投信 | ○ |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
LINE証券/株式投資がおすすめの理由
LINE証券/株式投資がおすすめの理由は「1株単位から取引ができる」「LINEアプリで取引ができる」という点です。
日常的に使うアプリ「LIINE」でそのまま株式投資・ができるのがLINE証券の大きな特徴です。1株単位から取引ができ、キャンペーンなどで株プレゼントも積極的に行っているため、お小遣い稼ぎや少額からトレードをしたい初心者投資家におすすめの証券会社と言えます。
デメリットは、取引商品の数が少なく、大きく稼ぎたい人には不向きな点です。
LINE証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:35件
楽天証券は楽天銀行との連携で入金や出金がスムーズで、画面の見やすく操作が容易な点がオススメ。楽天証券の利用で楽天市場でのポイント倍率が上がったり、その他楽天サービスでの特典やキャンペーンにも影響があるため、楽天経済圏の方は利用する価値が大いにあります。また、楽天ポイントで投資信託の投資が可能で少額でリスクなく投資できる環境で、国内株式はもちろん米国株式や債券、為替等金融商品が充実しているため初心者からでも始めやすいです。
楽天証券は利用することによってポイントが貯まっていくので贔屓にしています。それ以外にも投資信託の銘柄数も非常に多く、特にアメリカを始めとする海外に投資したいときにはとても便利です。私は日本株以外にも海外の株式にも投資を行っていて、こちらを利用することで上手にポートフォリオを作ることができています。さらにグループ会社の楽天銀行の口座を開設しておくと、資金の移動も簡単にすることができます。楽天ポイントを貯めている人や、これから投資を始めようと考えている人にとって使いやすい証券会社としてお勧めです。
トレードツールの「マーケットスピード」が使いやすいです。業界別指数一覧やヒートマップなど、直感的にマーケットの状況が把握できる機能が特に優れていると思います。また、楽天証券のメディア「トウシル」は情報の質・量ともにレベルが高く、投資の初心者からベテランの方まで幅広くカバーする内容になっています。楽天証券独自のサービス(「楽ラップ」や投資信託など)を無理に薦める内容は見受けられず、中立的な立場からの分析・アドバイスになっている点も安心して利用できるポイントかと思います。
私が株式投資を始める際にはどこの証券会社がよいか全く知識がなかったので、当時口座開設のキャンペーンをしていた楽天証券を選択しました。同時に楽天銀行の口座を開設し、数千ポイントがもらえたと記憶しています。またわずかなことではありますが、楽天カード、楽天銀行と提携しているので振り込み手数料や金利などの優遇があります。取扱銘柄は国内は希望するものは全て買えましたが、米国などの企業で買えない銘柄がちょくちょくあります。
銘柄数も多く、最新の流行りの商品といったものは導入も早く銘柄選択には困りません。メンテナンスが定期的に入っており、今までバグなどに出くわした事がないのも信頼ができます。
デメリットと感じているのは、米国株を取引している時に、メンテナンス時間が被ってしまい取引が出来なくなるタイミングがよくある事や、一部分だけスマートフォンに対応していなくスマートフォンで利用しているといきなりPC画面に飛んでしまったり操作がやりづらい事があります。

auカブコム証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 3
-
- 手数料の安さ
- 4
-
- 取扱銘柄の多さ
- 3
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 4
-
- サービスの利便性
- 3
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | auカブコム証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■ワンショット(1注文制) ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 100万円~:約定金額×0.099%+99円【上限:4,059円】 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■一日定額手数料 ~100万円:0円 ~200万円:2,200円 ~300万円:3,300円 ~400万円:4,400円 ~500万円:5,500円 500万円~:100万円毎に1,100円加算 |
| 開設口座数 | 1,354,125口座 ※2021年11月時点 |
| IPO実績(直近年間) | 19社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・FX ・取引所CFD ・ロボアド |
| 外国株 | 米国株式 |
| 米国株(銘柄数) | 200銘柄 |
| 投資信託数 | 1,497銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 163銘柄 |
| 取引ツール | ・kabuステーション ・カブナビ ・カブボード ・カブボードフラッシュ ・EVERチャート ・kabuスコープ ・kabuカルテ |
| アプリ | ・kabu.com for iPhone/Android/au ・カブボード ・カブボードフラッシュ ・kabu smart ・fund square for iPhone/Android (ファンドスクエアアプリ) |
| ポイント投資 | Pontaポイント |
| ポイント付与 | Pontaポイント |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
auカブコム証券/株式投資がおすすめの理由
auカブコム証券/株式投資がおすすめの理由は「情報発信の質が高い」「取引ツールが優秀」という点です。
auカブコム証券では、Youtubeでの情報発信や個人投資家向けのイベントなどの情報発信を積極的に行っています。また、銘柄のスクリーニング機能、取引ツールの機能性も高く、中級者以上の投資家におすすめできる証券会社となっています。
また、auユーザーへの特典も豊富に用意されています。
デメリットは、外国株の銘柄数が少なく、手数料も若干割高になっています。
auカブコム証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:9件
auユーザーにとっては比較的に簡単に始められる証券会社だと思います。じぶん銀行口座を持っていれば入出金の手数料も無料です。又、投資資金としてpontaポイントも使用出来る為、ポイントの有効活用にも繋がります。半面、パソコンから操作する場合は情報も解りやすく簡単に操作が出来ますが、スマートフォンからの場合、アプリの情報だけでは判断する情報が乏しく、使いづらいと感じています。今後、積み立てNISA等の投資信託も初めてみたいと思います。
auカブコム証券はプチ株があるから分散投資ができることが最大の強みだと感じました。大学生や資金のあまりない方でも株式投資を開始できることはかなり良いことだと思います。もちろんNISA口座も作ることができる為、税金面もばっちりですね。少し残念な点としてはSBIなどに比べてホーム画面が少しわかりづらいと思いました。イメージ的にはごちゃごちゃしていてどこに入金、出金などがあるかわわかりづらくそこはSBIに負けていると感じました。また初回設定のパスワードも郵送だったのでHTMLファイルで送ってほしい。また郵送である分口座開設から取引開始まで少し時間がかかった印象です。とは言っても総合評価は良いと思います。
数多くある証券会社の中から、カブコムを選んだのは、使い勝手が良いことに加えて、情報収集も早くて参考にできるからです。これまでにも、私自身、証券会社を使った経験がありますが、ここまで高品質なところはありませんでした。
カブコムの良さは、取引のしやすさもあると思います。昔のように、証券会社の担当者を介することなく、注文が可能です。私が特に気に入っているのは、ただ単に有望銘柄などの紹介に終わることなく、具体的な買い時売り時のアドバイスもしてくれることです。
全くの初心者から始めました。ビギナーズラックか、適当に買っていてもそこそこの利益がでたのです。当時のカブドットコムでの売買が容易で使いやすかった影響もあると思います。チャート画面が非常に見やすく売買に集中できたのです。この点はauカブコムに変わってから更に磨きがかかったと思います。しかし、所詮は勉強不足の初心者、やがて損益は拡大し、売り時の決心がつかぬまま塩漬けにする株も増えてしまいました。暫くは売買も自制しシミュレート売買のみで勉強を続けたこともありました。現在も継続できているのは、やはりインターフェースの良さ、使っていて楽しい、ストレスを感じないからだと思います。株を始めるにも、深く関わるにも、auカブコムは最適ではないでしょうか。
おおきな特徴としてあげられるのは多彩な注文方法だと思います。
注文方法は指値や逆指値、成行注文が代表的で多くの証券会社がこの3つのみとなっていますが、カブドットコム証券はWターン、トレーディングストップ、時間指定など多くあります。
これら特殊注文の多くは自動で発注や取り消しなどをしてくれるため、日中の取引が始まる前などに注文予約をして置くことができ、日中仕事で株価を見ることができない私にとってはとてもありがたいシステムになっています。
またFXにおいても自動売買のシストレFXがあるなど充実しており忙しい方におすすめです。

マネックス証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 5
-
- 手数料の安さ
- 3
-
- 取扱銘柄の多さ
- 5
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 5
-
- サービスの利便性
- 4
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | マネックス証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■取引毎手数料コース ~10万円:110円 ~20万円:198円 ~30万円:275円 ~40万円:385円 ~50万円:495円 ~100万円:成行注文/1,100円 指値注文/1,650円 100万円~:成行注文/約定金額の0.11% 指値注文/約定金額の0.165% ※マネックストレーダー株式 スマートフォンの場合、50万円~:約定金額の0.11% |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■一日定額手数料コース ~100万円:550円 100万~:300万円ごとに2,750円 月間利用ボックス(約定金額300万円ごとの売買)数:21回目からは2,475円 121回目からは1,815円 |
| 開設口座数 | 1,708,735口座 ※2021年12月末 |
| IPO実績(直近年間) | 65社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・暗号資産CFD ・おまかせ運用サービス ・外貨建てMMF ・先物 ・オプション ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・金・プラチナ |
| 外国株 | 米国株式 |
| 米国株(銘柄数) | 5,000銘柄 |
| 投資信託数 | 1,241銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 152銘柄 |
| 取引ツール | ・マネックストレーダー ・MonexTraderFX ・マルチボード500 ・チャートフォリオ ・フル板情報ツール |
| アプリ | ・マネックストレーダー株式スマートフォン ・マネックス証券アプリ ・トレードステーション米国株スマートフォン ・SNS型投資アプリ「ferci」 ・マネックストレーダーFXスマートフォン |
| ポイント投資 | – |
| ポイント付与 | マネックスポイント |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
マネックス証券/株式投資がおすすめの理由
マネックス証券/株式投資がおすすめの理由は「米国株に強い」「IPOに強い」という点です。
マネックス証券は、米国株で1位、2位を争うトップレベルの取扱商品数があり、米国株取引でおすすめできる証券会社となっています。
また、優秀な独自レポートや企業分析ツール、IPOの実績が豊富というメリットがあり、IPO狙いの投資家、分析を重視したい投資家にも定評がある証券会社となっています。
デメリットは、取引手数料が若干割高という点です。
マネックス証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:20件
IPOで株式を取得、初のIPOで取得した企業だけに思い入れがあります。相場状況などメールなどで送られてくる情報も信頼性が高く投資未経験の方にも分かりやすく解説されていると思います。またネット証券のパイオニアである意識も高いことからツール等の使い勝手もよく投資ビギナーの方にも安心して取引ができる環境を作っていると思います。最近はFXや仮想通貨の取引もできるようになり株式以外の取引も検討できるようになり投資ビギナー向けの証券会社としてはお勧めできる会社だと思います。
初めての株購入ということで、購入までのハードルが高過ぎたらどうしようと不安でしたが、意外とすんなり購入できて、それはそれで大丈夫か?と思ったのが最初です。まずは投資用の口座開設ですが、預金銀行先と連携されているため、簡単に開設できました。お目当ての投資先を検索後は、購入するだけですが、気になったりわからない文言などは説明があったので助かりました。
長期取引のため、購入後はほったらかしですが、先日チェックしたら赤字になっていました。しかし、今後の巻き返しをのんびり期待したいと思っています。
本来は単元株(100株)ごとの購入だが、マネックス証券には1株から購入できるワン株というものがあり、しかも購入時の手数料が0円になっている。単元未満株は儲からないと言われてはいるが、元本が少ない人でも、初心者でも長期的に買い増しができ、リスクも単元株で購入するよりも少ないのでお勧め。自分もワン株を中心に投資をしているが、それなりにプラスにはなっている。すぐに大きく儲けようと思わなければ購入手数料0円はかなり魅力的だと思う。
マネックス証券を利用しています。他の証券会社を試したことがないので、正確な比較はできませんが、手数料は他の証券会社の方が低いところがあるようです。しかしながら、銘柄分析ツール(マネックス銘柄スカウター)はかなり使いやすく重宝しています。この分析ツールは国内株だけでなく、アメリカ株、中国株に関してもあるので、米国株や中国株を買いに行くときにも利用できるので、大変助かっています。また、アナリストのレポートなども閲覧できるので、私個人としてはかなり使いやすい証券会社かなと思っています。
マネックス証券の良い点として、アプリはとても使いやすいと思います。まず。保有資産、損益などをグラフで表示し、次に投資した方がいいものをアドバイスしてくれます。また、アプリ上から投資に役立つ情報を見ることができ、とても勉強になります。
次にマネックス証券の悪い点は、入金、出金がしにくいところで、時間がかかります。即時入金を望む人はお勧めしません。あと、外国株はマネックス証券の別アプリを用意しないといけないのも難点だと思います。

松井証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 5
-
- 手数料の安さ
- 5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 3
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 3
-
- サービスの利便性
- 3
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | 松井証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | – |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■ボックスレート(1日定額制) ~50万円:0円 ~100万円:1,100円 ~200万円:2,200円 ~1億円:100万円単位で1,100円加算 1億円~:110,000円(上限) ※25歳以下はすべて無料 |
| 開設口座数 | 1,401,205口座 ※2021年12月末 |
| IPO実績(直近年間) | 56社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・先物 ・オプション ・外国為替証拠金取引(FX) ・iDeCo(個人型確定拠出年金) |
| 外国株 | 米国株式 |
| 米国株(銘柄数) | 395銘柄 |
| 投資信託数 | 1,581銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 172銘柄 |
| 取引ツール | ・ネットストック・ハイスピード ・株価ボード ・チャートフォリオ ・アクティビスト追跡ツール ・フル板情報 |
| アプリ | ・松井証券 株アプリ ・株touch ・投信アプリ ・松井証券 FXアプリ |
| ポイント投資 | 松井証券ポイント |
| ポイント付与 | 松井証券ポイント |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
松井証券/株式投資がおすすめの理由
松井証券/株式投資がおすすめの理由は「取引手数料が無料」という点です。
松井証券では、現物株の取引手数料が50万円まで無料、一日信用取引でも取引手数料が無料と、無料条件に合致した方であれば、手数料無料で株式投資ができるメリットがあります。一切、コストをかけずにトレードできるのは大きな魅力と言っていいでしょう。
また、ネット証券ではないため、問い合わせ対応などが丁寧な点も、魅力の一つと言えます。
デメリットは、外国株、ETF、債権などの商品ラインナップが少ない点です。また、約定代金が大きくなると無料条件から外れてしまい、逆に割高な取引手数料が発生してしまう点です。
松井証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:18件
松井証券の株タッチのアプリを使いながら株式投資をしています。
日々の取引はあまり行ってませんが、株式の情報を得るために利用してます。
株式ランキングを見るときも株式の市場を選択出来たり、種類(値上がり率上位、ストップ高など16種類から)選択できるので、私には使い勝手が良いです。
ニュースも細かく書かれており、情報を得るのに分かりやすいです。
個別にアドバイスをくれたりすると面白いと思います。
(AIの技術とかでできるのでは?)
初心者むけにぴったしの口座です。私が選んだ理由は1日10万円以下なら手数料は無料です。取引等で分からないことがあれば、サポート(ヘルプ)に電話すれば、親身になって丁寧にアドバイスをしてくださいます。ネットストックハイスピード・携帯の電話のアプリなどとても使いやすく、私は取引ではパソコンだけなく形態のアプリも使用しています。携帯のアプリは取引情報だけでなくチャートや移動平均線なども見やすく自分の使いやすいように設定可能です
松井証券は1日50万円までの手数料が0円となっており、ちょっとした3桁台の株価の銘柄を売買したりするときに使っています。他の証券会社では100万円まで0円のところもあるのでやや微妙なところはありますが、100万円までは取引することも少ないので、特に苦にはなっていません。
また松井証券ではIPO投資でも利用しています。最近は幹事になるケースも増えてきているほか、前受け金不要のシステムを採用しており、他の証券会社にはない魅力もあります。
12年程前に数冊の株式投資の本を読んで株式投資を始めました。小額の元手で大きく増やしたければ、手数料の少ない会社でデイトレードやスウィングトレードを繰り返すしかないと思い、手数料の少ない会社として松井証券を選びました。それまで、名前も知りませんでした。2、3年前までは1日に10万円未満の取引は手数料無料でしたが、現在は1日に50万円未満取引無料に変わり、よりよくなっていると思います。問い合わせにもメール対応しかしない会社もある中で、電話対応してくれるのもやはり安心要素です。
株式投資を始めて12年ほどになります。やり方が全く分からなかったので、初心者向けの株式投資の本を購入しました。松井証券は私が投資しようと思う金額の範囲では手数料が0円となっており、とりあえず多額の投資をする気はなかったので松井証券に決めました。
最初の頃は頻繁に売り買いをしていたのですが、時間も取られるので、最近は安定的に配当している株を保有しています。また、近所のスーパーの株は配当がある上に購入額に対する株主優待が魅力的でしたので食品はここで買うと決めています。銀行の預金利息よりはるかに多くの配当金で満足しています。

岡三オンライン/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 4
-
- 手数料の安さ
- 5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 3
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 5
-
- サービスの利便性
- 3
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | 岡三オンライン |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■ワンショット(1約定制) ~10万円:108円 ~20万円:220円 ~50万円:385円 ~100万円:660円 ~150万円:1,100円 ~300万円:1,650円 以降100万円ごとに330円 ※上限3,300円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■定額プラン(1日定額制) ~100万円:0円 ~200万円:1,430円 以降100万円ごとに550円 |
| 開設口座数 | 289,660口座 ※2021年11月末 |
| IPO実績(直近年間) | 47社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・先物 ・オプション ・くりっく365 ・くりっく株365 ・iDeCo(個人型確定拠出年金) |
| 外国株 | 中国株式 |
| 米国株(銘柄数) | – |
| 投資信託数 | 552銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | – |
| 取引ツール | ・岡三ネットトレーダーシリーズ ・岡三ネットトレーダーWEB2 ・岡三かんたん発注 ・岡三RSS |
| アプリ | ・岡三カブスマホ ・岡三ネットトレーダースマホ |
| ポイント投資 | 松井証券ポイント |
| ポイント付与 | 松井証券ポイント |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
岡三オンライン/株式投資がおすすめの理由
岡三オンライン/株式投資がおすすめの理由は「取引手数料が無料」「情報コンテンツの質が高い」という点です。
岡三オンラインでは、約定代金100万円以下であれば取引手数料が無料でトレードすることができます。
また、会社分析情報、市場分析情報、アナリストレポートなどの情報発信の質が高く、情報コンテンツに定評があり、多くの投資家が情報収集目的で利用している証券会社でもあります。
デメリットは、商品ラインナップが少ない点です。
岡三オンライン/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:6件
10年以上、松井証券で取引をしていますが、とくに大きな不満はありません。
一日の約定代金合計金額50万円までは手数料無料のため、私のようにたまに少額銘柄を売買をする人間にとっては手数料がタダ同然なので助かっています。
投資判断に便利なツールもあるので、銘柄選びに活用できて便利です。
スマホ向けアプリもあるので、スマホ1台で取引ができるのでお手軽なのもおススメです。
1つだけ不満なのは、アプリ上で保有銘柄一覧を確認できるのが売買画面だけなので、銘柄を確認したいだけなのにうっかり株式売買に進んでしまうことがあることです。
その1点を除けば、非常に使いやすく信頼できる証券会社さんです。
取引金額が少なければ、手数料が無料になる場合もあるので、初心者には適していると思います。また、サポート体制もばっちりで、こちらかの質問に対して、納得するまで分かりやすく丁寧に応えてくれるので助かります。また、パソコンだけでなく、スマホのアプリもあるので、手軽に取引ができますし、アプリも企業情報やチャートも見れるので、個人的には重宝しています。ただ、トレードツールが他の証券会社に比べて少ないような気がします。初心者には松井証券はばっちりです。
現物と信用のいずれの取引においても、同業他社の手数料と比較して安く、少額での取引体験を積み上げられています。しかも、コールセンターでの対応はいつも丁寧だと思います。例えば、銘柄選択の相談をした際には、こちらの考えや予測を聞いたうえで、今後の予想を詳細に説明頂きました。初心者であっても雑に扱われることもなく、利用しやすさを感じています。また、取引ツールもスマホ、PC、タブレットと時間や状況に応じた利用が可能なことも利便性を感じています。
株式投資をやってみようと思った際にとても魅力的な条件だったので口座開設をしました。社長がとても先進的で、既存の会社とは一線を画した仕組みであったり、手数料だったりで業界の最先端を感じました。その後も、トレードツールだったり、トレード条件に関しても新しい提案をされる会社で、使用していてとても楽しいです。
一度、超短時間で取引をする手法を試したこともありますが、レスポンスも早いため、使い勝手もとても良かったです。
まず、少額の場合は手数料が無料になります(50万円まで)。使い勝手に関しては、特にこれといったものはありません。自分がまだこちらしか証券サイトは使ったことが無いため、他の所は分かりませんが、やや注文の際の認証が面倒な感じがします。(パスワードともう一つ別の文字列を入寮する必要がある。合計で3つの文字を覚える必要がある。)国内の株式ならば銘柄を検索して、資金のうちで買い、売りの注文が出来、チャートボードでは必要なチャートをいつでも見られるようにできます。
ただ、海外株に関しては他の会社に比べて品数が少ないです。
つまりは初心者が国内株式の売買を行うにはもってこいの証券サイトです。

DMM.com証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 4
-
- 手数料の安さ
- 5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 3
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 3
-
- サービスの利便性
- 3
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | DMM.com証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■1約定制 ~5万円:55円 ~10万円:88円 ~20万円:106円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 ~150万円:440円 ~300万円:660円 300万円~:880円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | – |
| 開設口座数 | 非公開 |
| IPO実績(直近年間) | 5社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・外国為替証拠金取引(FX) ・CFD(くりっく株365) |
| 外国株 | 米国株式 |
| 米国株(銘柄数) | 1,513銘柄 |
| 投資信託数 | 300銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | – |
| 取引ツール | ・DMM株 PRO+ ・DMM株 STANDARD ・DMM株 PRO |
| アプリ | ・スマホアプリ DMM株 |
| ポイント投資 | DMM 株ポイント |
| ポイント付与 | DMM 株ポイント |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
DMM.com証券/株式投資がおすすめの理由
DMM.com証券/株式投資がおすすめの理由は「米国株取引の取引手数料が無料」という点です。
DMM.com証券/株式投資は、無条件で「米国株取引の取引手数料が無料」というサービスをかかげています。一切お金をかけずに米国株取引ができるのです。
また、最短即日で口座開設・取引ができるため利便性も高く、米国株式を担保に国内株式の信用取引が可能、米国株と国内株を同時に取引できる高機能トレードツールあり、と米国株取引を行う投資家におすすめの証券会社となっています。
DMM.com証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

GMOクリック証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 2.5
-
- 手数料の安さ
- 3.5
-
- 取扱銘柄の多さ
- 2.5
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 2.5
-
- サービスの利便性
- 2.5
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | GMOクリック証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■1約定ごとプラン ~5万円:50円 ~10万円:90円 ~20万円:100円 ~50万円:260円 ~100万円:460円 ~150万円:550円 ~3,000万円:880円 3,000万円~:930円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■定額プラン ~100万円:0円 ~200万円:1,238円 ~300万円:1,691円 300万~:以降100万円ごとに295円 |
| 開設口座数 | 481,831口座 ※2022年1月末 |
| IPO実績(直近年間) | 1社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・オプション ・バイナリーオプション ・CFD |
| 外国株 | – |
| 米国株(銘柄数) | – |
| 投資信託数 | 135銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | – |
| 取引ツール | ・スーパーはっちゅう君 ・はっちゅう君 |
| アプリ | ・GMOクリック 株 |
| ポイント投資 | – |
| ポイント付与 | – |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
GMOクリック証券/株式投資がおすすめの理由
GMOクリック証券/株式投資がおすすめの理由は「使いやすい」「CFD取引が充実している」点です。
GMOクリック証券は、使いやすい取引ツールを多く用意しており、使いやすいアプリ、高度なテクニカル分析ができる取引ツールなど、初心者でも使いやすいメリットがある証券会社です。
また、CFD取引やバイナリーオプションなど、他社が扱っていない取引商品も多く、取引商品・取引方法の選択肢も豊富な証券会社です。
デメリットは、外国株の取引ができない、IPO実績がほぼない点です。
GMOクリック証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:0件

SBIネオトレード証券/株式投資

-
- 企業の信頼性
- 2.5
-
- 手数料の安さ
- 4
-
- 取扱銘柄の多さ
- 2
-
- トレードツールの機能・使いやすさ
- 2.5
-
- サービスの利便性
- 2
| サービス名 | 株式投資 |
|---|---|
| 運営会社 | SBIネオトレード証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■一律プラン ~5万円:50円 ~10万円:88円 ~20万円:100円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 ~150万円:440円 ~300万円:660円 300万円~:880円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■定額プラン ~100万円:0円 ~150万円:880円 ~200万円:1,100円 ~300万円:1,540円 300万~:以降100万円ごとに+295円 |
| 開設口座数 | 非公開 |
| IPO実績(直近年間) | 20社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・投資信託 ・先物 |
| 外国株 | – |
| 米国株(銘柄数) | – |
| 投資信託数 | 10銘柄 |
| NISA | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 1銘柄 |
| 取引ツール | ・NEOTRADE R ・株価ボード |
| アプリ | ・Android版アプリ NEOTRADE S ・iPhone版アプリ NEOTRADE S |
| ポイント投資 | – |
| ポイント付与 | – |
| クレジットカード積立投信 | – |
| 公式 | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 |
SBIネオトレード証券/株式投資がおすすめの理由
SBIネオトレード証券/株式投資がおすすめの理由は「取引手数料が安い」「IPOが利用しやす」点です。
SBIネオトレード証券では、100万までの取引手数料が無料、信用取引の取引手数料が無料と信用取引の取引手数料が無料の珍しいサービスを展開しています。信用取引を行う中級者以上の投資家におすすめできる証券会社となっています。
また、事前入金なしでIPOに申し込めるため、資金力がなくても、IPOの抽選に参加できるメリットがあります。
デメリットは、米国株をはじめとする外国株の取引ができない、投資信託の取扱銘柄数も少ない点です。
SBIネオトレード証券/株式投資の口コミ
最新口コミ 口コミ投稿数:15件
■一番の利点は、資金だけでなく、Tポイントが使えるということ
Tポイントは毎月200円手数料で引かれるが、同じ200Tポイントとして付与されるので実質0円で投資をし続けられるのが、最も気に入っている点です。
■最も不便な点は、単元未満株(100株に満たない時)は、指し値注文ができないということ
単元未満株は、指し値注文ができないです。その為、前場もしくば後場での成り行きでしか注文することができません。
私は、高配当株銘柄投資家です。つまりリストアップした目ぼしい銘柄の株価が下がった時に買い付ける。そしてよっぽどの不祥事・業績悪化が起こらないと売却しません。
私のような、長期でコツコツと積み上げていくタイプの投資家さんに向けては、最適だと思います。単元未満株の指し値注文はできませんが、基本売らないので、大体の安値で購入できれば、大した問題にならないのではないでしょうか。
国内大手の1株から購入可能でバリュエーション豊かな銘柄種類と、手数料が低い、ティポイント、配当も受けられるなどの特徴があるで投資初心者も始めやすいと思います。売買手数料は無料な反面、毎月220円コストかかる(ティポイントで同額を還元されますが)ので、目的によってはあえて利用する必要はないかもしれません。
売買時の価格が分かりにくいので、その点はマイナスですね。
高配当銘柄目的なら、あまりお勧めはしません。
手軽に始められてよい。アプリの画面も見やすい。個別銘柄の検索も、比較的探しやすい。特に株主優待が受けれる銘柄を検索できることは便利だ。しかし、操作をしていると、すぐにブラウザへ遷移することが難点。あまりアプリの意味がないのではないか。できるだけアプリ内で完結するようにしてほしい。Tポイントを使って投資できるのはいいが、そもそも貯まっているポイント数が低すぎて、投資で使おうと思わない。本当に投資初心者で数千~数万円ぐらいの取引しかしない人にはちょうどいいかもしれない。
主に国内高配当株投資のために利用しています。1株単位で国内株式が購入できるので資金が少ない私にとっては分散投資をした私には好都合でした。外国株式も同時に購入したかったので私はSBI証券とSBIネオモバイル証券を同時に開設し投資をしています。SBIネオモバイル証券は毎月の手数料はかかりますが、Tポイントで還元されるのでコストを抑えたい方には特におすすめです。発注の時間帯によって約定価格が異なる点と、成行注文しかできな点は注意ポイントです。
SBIネオモバイル証券は日本株を毎月50万円以下で取引するのであれば取引手数料は一律の220円+投資に回せる期間限定Tポイントが200ポイントが付与されるという破格の取引コストの安さが魅力であると思います。
投資信託ではなく実際に企業株をS株単位で購入できるため、大きな資金はないがゆくゆくはある企業の優待を受けたい等の取引初心者の方や、日本株の高配当株式に分散投資をコツコツしていき、最終的には月換算で例えば5万円の配当金を得られるポートフォリオを作成してみたいというような長期志向の方にお勧めできる証券会社です。(取引がない月にも220円の取引手数料は取られるため、ある程度長期目的を持ち少額でも毎月取引する人が向いていると思います)
このような特徴のため大口の取引をしたい方はあまり向いていないと思います。
例えば次の50万超から300万以下は月で1100円の取引手数料がかかってきます。300万を月に取引する方はおそらく初心者や長期目線での取引の方では少ないと思いますので他の証券会社を利用したほうが結果的に手数料が安くなるのではないかと思います。
また日本株式のみですので、他の新興国などに投資したい方は最初から対象外となります。
ツールに関しては他の証券会社と比較するとあまり機能は揃っていないと感じますが個人的にツールノウハウがあるわけではないのであくまで主観的な感想です。また長期目線の方や初心者の方にはツールの豊富さや使い勝手はさほど影響のないと感じてもいます。これも主観です(笑)
「株式投資」おすすめ証券会社比較
| サービス名 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 | 株式投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | SBI証券 | 楽天証券 | LINE証券 | auカブコム証券 | マネックス証券 | 松井証券 | 岡三オンライン | DMM.com証券 | GMOクリック証券 | SBIネオトレード証券 |
| 株式売買手数料:1約定ごと | ■スタンダードプラン ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 | ■超割コース ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 | ■超割コース ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 ~150万円:640円 ~3,000万円:1,013円 3,000万円~:1,070円 | ■ワンショット(1注文制) ~5万円:55円 ~10万円:99円 ~20万円:115円 ~50万円:275円 ~100万円:535円 100万円~:約定金額×0.099%+99円【上限:4,059円】 | ■取引毎手数料コース ~10万円:110円 ~20万円:198円 ~30万円:275円 ~40万円:385円 ~50万円:495円 ~100万円:成行注文/1,100円 指値注文/1,650円 100万円~:成行注文/約定金額の0.11% 指値注文/約定金額の0.165% ※マネックストレーダー株式 スマートフォンの場合、50万円~:約定金額の0.11% | – | ■ワンショット(1約定制) ~10万円:108円 ~20万円:220円 ~50万円:385円 ~100万円:660円 ~150万円:1,100円 ~300万円:1,650円 以降100万円ごとに330円 ※上限3,300円 | ■1約定制 ~5万円:55円 ~10万円:88円 ~20万円:106円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 ~150万円:440円 ~300万円:660円 300万円~:880円 | ■1約定ごとプラン ~5万円:50円 ~10万円:90円 ~20万円:100円 ~50万円:260円 ~100万円:460円 ~150万円:550円 ~3,000万円:880円 3,000万円~:930円 | ■一律プラン ~5万円:50円 ~10万円:88円 ~20万円:100円 ~50万円:198円 ~100万円:374円 ~150万円:440円 ~300万円:660円 300万円~:880円 |
| 株式売買手数料:1日定額 | ■アクティブプラン ~100万円:0円 ~200万円:1,238円 ~300万円:1,691円 以降100万円ごとに:295円 | ■いちにち定額コース ~100万円:0円 ~200万円:2,200円 ~300万円:3,300円 300万円~:以降100万円ごとに1,100円 | – | ■一日定額手数料 ~100万円:0円 ~200万円:2,200円 ~300万円:3,300円 ~400万円:4,400円 ~500万円:5,500円 500万円~:100万円毎に1,100円加算 | ■一日定額手数料コース ~100万円:550円 100万~:300万円ごとに2,750円 月間利用ボックス(約定金額300万円ごとの売買)数:21回目からは2,475円 121回目からは1,815円 | ■ボックスレート(1日定額制) ~50万円:0円 ~100万円:1,100円 ~200万円:2,200円 ~1億円:100万円単位で1,100円加算 1億円~:110,000円(上限) ※25歳以下はすべて無料 | ■定額プラン(1日定額制) ~100万円:0円 ~200万円:1,430円 以降100万円ごとに550円 | – | ■定額プラン ~100万円:0円 ~200万円:1,238円 ~300万円:1,691円 300万~:以降100万円ごとに295円 | ■定額プラン ~100万円:0円 ~150万円:880円 ~200万円:1,100円 ~300万円:1,540円 300万~:以降100万円ごとに+295円 |
| 開設口座数 | 約7,717,000口座 ※2021年9月末(SBIネオモバイル証券,SBIネオトレード証券含む) | 6,243,338口座 ※2021年6月末 | 約100万口座 ※2021年10月時点 | 1,354,125口座 ※2021年11月時点 | 1,708,735口座 ※2021年12月末 | 1,401,205口座 ※2021年12月末 | 289,660口座 ※2021年11月末 | 非公開 | 481,831口座 ※2022年1月末 | 非公開 |
| IPO実績(直近年間) | 85社 | 38社 | 11社 | 19社 | 65社 | 56社 | 47社 | 5社 | 1社 | 20社 |
| 取扱商品 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・オプション ・CFD(くりっく株365) ・金・銀・プラチナ ・eワラント ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・保険 | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・バイナリーオプション ・FX ・CFD ・金・銀・プラチナ ・eワラント ・iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・国内株式 ・投資信託 ・iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・国内株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・FX ・取引所CFD ・ロボアド | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・暗号資産CFD ・おまかせ運用サービス ・外貨建てMMF ・先物 ・オプション ・iDeCo(個人型確定拠出年金) ・金・プラチナ | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・先物 ・オプション ・外国為替証拠金取引(FX) ・iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・先物 ・オプション ・くりっく365 ・くりっく株365 ・iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・国内株式 ・外国株式 ・投資信託 ・外国為替証拠金取引(FX) ・CFD(くりっく株365) | ・国内株式 ・投資信託 ・債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・先物 ・オプション ・バイナリーオプション ・CFD | ・国内株式 ・投資信託 ・先物 |
| 外国株 | 米国株式、インドネシア株式、中国株式、シンガポール株式、韓国株式、タイ株式、ロシア株式、マレーシア株式、ベトナム株式 | 米国株式、インドネシア株式、中国株式、シンガポール株式、タイ株式、マレーシア株式 | – | 米国株式 | 米国株式 | 米国株式 | 中国株式 | 米国株式 | – | – |
| 米国株(銘柄数) | 302銘柄 | 4,484銘柄 | – | 200銘柄 | 5,000銘柄 | 395銘柄 | – | 1,513銘柄 | – | – |
| 投資信託数 | 2,650銘柄 | 2,664銘柄 | 32銘柄 | 1,497銘柄 | 1,241銘柄 | 1,581銘柄 | 552銘柄 | 300銘柄 | 135銘柄 | 10銘柄 |
| NISA | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 積立NISA(銘柄数) | 174銘柄 | 179銘柄 | – | 163銘柄 | 152銘柄 | 172銘柄 | – | – | – | 1銘柄 |
| 取引ツール | ・HYPER SBI ・SBI CFDトレーダー | ・マーケットスピード2 ・マーケットスピード ・マーケットスピード for Mac ・マーケットスピード II RSS ・マーケットスピードFX ・楽天MT4 | ・LINE | ・kabuステーション ・カブナビ ・カブボード ・カブボードフラッシュ ・EVERチャート ・kabuスコープ ・kabuカルテ | ・マネックストレーダー ・MonexTraderFX ・マルチボード500 ・チャートフォリオ ・フル板情報ツール | ・ネットストック・ハイスピード ・株価ボード ・チャートフォリオ ・アクティビスト追跡ツール ・フル板情報 | ・岡三ネットトレーダーシリーズ ・岡三ネットトレーダーWEB2 ・岡三かんたん発注 ・岡三RSS | ・DMM株 PRO+ ・DMM株 STANDARD ・DMM株 PRO | ・スーパーはっちゅう君 ・はっちゅう君 | ・NEOTRADE R ・株価ボード |
| アプリ | ・SBI証券 株アプリ ・SBI証券 米国株アプリ ・かんたん積立 アプリ ・HYPER FXアプリ ・HYPER 先物/オプションアプリ ・HYPER CFDアプリ | ・iSPEED ・iSPEED for iPad ・iSPEED FX ・iSPEED 先物 | ・LINE | ・kabu.com for iPhone/Android/au ・カブボード ・カブボードフラッシュ ・kabu smart ・fund square for iPhone/Android (ファンドスクエアアプリ) | ・マネックストレーダー株式スマートフォン ・マネックス証券アプリ ・トレードステーション米国株スマートフォン ・SNS型投資アプリ「ferci」 ・マネックストレーダーFXスマートフォン | ・松井証券 株アプリ ・株touch ・投信アプリ ・松井証券 FXアプリ | ・岡三カブスマホ ・岡三ネットトレーダースマホ | ・スマホアプリ DMM株 | ・GMOクリック 株 | ・Android版アプリ NEOTRADE S ・iPhone版アプリ NEOTRADE S |
| ポイント投資 | Tポイント、Pontaポイント | 楽天スーパーポイント | LINEポイント | Pontaポイント | – | 松井証券ポイント | 松井証券ポイント | DMM 株ポイント | – | – |
| ポイント付与 | Tポイント、Pontaポイント、Vポイント | 楽天スーパーポイント | – | Pontaポイント | マネックスポイント | 松井証券ポイント | 松井証券ポイント | DMM 株ポイント | – | – |
| クレジットカード積立投信 | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
| 口コミ | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 | 口コミ・評判 |
「株式投資」でおすすめの証券会社ランキング/利用した方の口コミ・評判
口コミ・評判ランキングは、口コミ件数5件以上で、総合評価順に表示しています。口コミ件数5件未満のものは、口コミ件数が多い順に表示しています。
SBI証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.6点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:80件
株に対して知識がない私が株を始めたきっかけは、ネット証券というものが出来てゲーム感覚で始められると思ったからです。まだネット証券は数社しかなかった頃、一番手数料が安かったイー・トレード証券、現SBI証券を選びました。デイトレーダーが、数分間でいくら儲けたとか、そんなことが話題になった時代です。SBI証券は一ヶ月間、1度でも取引があればトレーディングツールを無料で使うことが出来たので、それもデイトレードするのには最適な環境でした。HYPER SBI というトレーディングツールですが使いやすいです。また、住信SBIネット銀行の口座があれば、銀行の振込手数料が無料になるのがとてもお得です。
はっきり言ってしまって、特にこれが大きな特徴というトレード上のメリットとかがあるわけではないのですがIPOに関しては抽選に落ちてもポイントがもらえて物凄くたくさん貯めないといけないのですが、それによって優先権をもらえるというのはよいですね。サポートとかそもそもあんまり問い合わせたことがないのでわかりませんが、悪くはないとは思います。SBIネット銀行と紐づけさせることができるのがとても便利ではあります。
初めて開設した証券会社の口座でした。優待目的でオリックスやスカイラークの株を持っていました。
また米国株の投資信託をクレジットカード決済で購入しておりかなりお得です。
サービスの改悪が続いている証券会社もある中、SBI証券はサービスの向上を続けており、今後もメインバンクとして何十年と渡って使用していきたいと思っています。
IPO投資も行っており、SBI証券はIPOの抽選に外れるとポイントが貯まりいずれは当選することができるので、他社にはない強みだと思います。そのせいもあり、昔から一番よく使う証券会社です。
SBI銀行口座も開設することでお金の移動がスムーズにでき、引き下ろす際も手数料無料だったりかなり便利に使えました。
国内現物取引の手数料は業界最安値で他の追随を許さない。中長期取引もデイトレードにとってもやりやすい料金体系で、初心者も安心して利用できる。専用の取引ツールを使用せずとも公式ページの株式売買がシンプルで利用しやすい。わからないところがあればカスタマーサポートに電話すればすぐに繋がりやすくて親切なのも、業界最大手だけに余裕がある対応だと思う。少し残念なのは、取引の参考になる情報量がかなり少ないこと。口座を開設して10年を超えるが、メールをもらったのは数えるほどしかない。
口座開設、維持手数料が無料だったので口座を開設した。コストが安いことはもちろんのこと海外のETFや個別株もたくさん取引できるので、自分の思い通りにポートフォリオが作れる。また、時々キャンペーンでちょっとした投資資金をもらえるのも嬉しい。さらに、投資信託を保有することでTポイントやVポイントを貰えるプログラムもやっている。SBI証券と同様の楽天証券でも保有する投資信託に応じて楽天ポイントがもらえるが、SBI証券の方が還元率が良い。以上の点がSBI証券の長所だと考える。
楽天証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.7点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:125件
複数の証券会社を利用していますが、楽天証券のインターフェースが一番見やすくて使いやすいです。四季報も無料で読めたりと便利に使えます。最近の楽天全体の改悪によって投資信託を保有していることに対して付与されていたポイントが大幅に減ってしまったのは残念ですが、楽天カードと楽天キャッシュをあわせて10万円までキャッシュレス決済で投資信託を積み立てられるのはやはりメリットが大きいと思います。楽天銀行と併用すると普通預金でも0.1%の金利が得られることもよいと思います。
楽天証券で株式投資をしています。普段利用する商品をもらったりサービスの割引をしてくれる株主優待目当てで株を買いました。私は何かとズボラな性格で一度株を買うと何ヶ月もサイトを開かず放っておくことが多いです。楽天証券は決算発表のメールを送ってくれてわかるようになっているのがありがたいです。また楽天銀行との連携サービスであるマネーブリッジを利用しており楽天銀行から出入金時の手数料が無料になる、ポイントがたまるなどのサービスが充実しています。
投資歴は5年前に楽天証券ではない普段使いの労働金庫でのつみたてNISAを始め、一年少し前から楽天証券で全米インデックス連動の投資信託(楽天VTI)や、日本の高配当個別株、アメリカの高配当ETFへの投資を始めました。正直、店舗型よりもネット証券である楽天証券の方が各種手数料が安いことや、楽天経済圏どっぷりの生活を送っていることから、楽天証券での投資が様々なコスト、ポイントによる生活費の削減という観点から優れています。コロナ禍で始めた投資なので、その後の景気回復を受けどこの証券会社でも含み益は大きくなっていると思いますし、SBIなど手数料も安くポイントも改善される中、ポイント改悪の続く楽天ですが、国内大手経済圏の楽天の持つアドバンテージはまだまだ大きいと感じます。
まず手数料が安いです。一日100万円まで無料なので手数料がかかることが殆どありません。
マネーブリッジに登録すると楽天銀行から証券口座に随時に自動送金、自動返金されるので口座残高を気にせず済むのが便利に感じています。手数料もかかりません。
取引で楽天ポイントがそこそこ貯まること、貯まったポイントが使えるのも嬉しいです。最近ルールが改悪されてポイント還元率が下がったことと、期間限定ポイントは相変わらず使えないことは不満ですが。
楽天証券を使用しておりますが、口座開設までの流れ・手順が簡単でマイナンバーカードがあれば数日で証券口座を開設出来ました。スマホアプリで取引・管理が出来て、相場の動きも手軽に見れるので使いやすいです。また、アプリ内の検索フォームが充実していて自分が調べたい銘柄も色んな方法で検索出来ます。その他にも楽天市場などで溜まった楽天ポイントも購入時に使用可能なので普段から楽天を使っている方にはより便利だと思います。
松井証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.2点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:18件
松井証券の株タッチのアプリを使いながら株式投資をしています。
日々の取引はあまり行ってませんが、株式の情報を得るために利用してます。
株式ランキングを見るときも株式の市場を選択出来たり、種類(値上がり率上位、ストップ高など16種類から)選択できるので、私には使い勝手が良いです。
ニュースも細かく書かれており、情報を得るのに分かりやすいです。
個別にアドバイスをくれたりすると面白いと思います。
(AIの技術とかでできるのでは?)
初心者むけにぴったしの口座です。私が選んだ理由は1日10万円以下なら手数料は無料です。取引等で分からないことがあれば、サポート(ヘルプ)に電話すれば、親身になって丁寧にアドバイスをしてくださいます。ネットストックハイスピード・携帯の電話のアプリなどとても使いやすく、私は取引ではパソコンだけなく形態のアプリも使用しています。携帯のアプリは取引情報だけでなくチャートや移動平均線なども見やすく自分の使いやすいように設定可能です
松井証券は1日50万円までの手数料が0円となっており、ちょっとした3桁台の株価の銘柄を売買したりするときに使っています。他の証券会社では100万円まで0円のところもあるのでやや微妙なところはありますが、100万円までは取引することも少ないので、特に苦にはなっていません。
また松井証券ではIPO投資でも利用しています。最近は幹事になるケースも増えてきているほか、前受け金不要のシステムを採用しており、他の証券会社にはない魅力もあります。
12年程前に数冊の株式投資の本を読んで株式投資を始めました。小額の元手で大きく増やしたければ、手数料の少ない会社でデイトレードやスウィングトレードを繰り返すしかないと思い、手数料の少ない会社として松井証券を選びました。それまで、名前も知りませんでした。2、3年前までは1日に10万円未満の取引は手数料無料でしたが、現在は1日に50万円未満取引無料に変わり、よりよくなっていると思います。問い合わせにもメール対応しかしない会社もある中で、電話対応してくれるのもやはり安心要素です。
株式投資を始めて12年ほどになります。やり方が全く分からなかったので、初心者向けの株式投資の本を購入しました。松井証券は私が投資しようと思う金額の範囲では手数料が0円となっており、とりあえず多額の投資をする気はなかったので松井証券に決めました。
最初の頃は頻繁に売り買いをしていたのですが、時間も取られるので、最近は安定的に配当している株を保有しています。また、近所のスーパーの株は配当がある上に購入額に対する株主優待が魅力的でしたので食品はここで買うと決めています。銀行の預金利息よりはるかに多くの配当金で満足しています。
マネックス証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.4点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:20件
IPOで株式を取得、初のIPOで取得した企業だけに思い入れがあります。相場状況などメールなどで送られてくる情報も信頼性が高く投資未経験の方にも分かりやすく解説されていると思います。またネット証券のパイオニアである意識も高いことからツール等の使い勝手もよく投資ビギナーの方にも安心して取引ができる環境を作っていると思います。最近はFXや仮想通貨の取引もできるようになり株式以外の取引も検討できるようになり投資ビギナー向けの証券会社としてはお勧めできる会社だと思います。
初めての株購入ということで、購入までのハードルが高過ぎたらどうしようと不安でしたが、意外とすんなり購入できて、それはそれで大丈夫か?と思ったのが最初です。まずは投資用の口座開設ですが、預金銀行先と連携されているため、簡単に開設できました。お目当ての投資先を検索後は、購入するだけですが、気になったりわからない文言などは説明があったので助かりました。
長期取引のため、購入後はほったらかしですが、先日チェックしたら赤字になっていました。しかし、今後の巻き返しをのんびり期待したいと思っています。
本来は単元株(100株)ごとの購入だが、マネックス証券には1株から購入できるワン株というものがあり、しかも購入時の手数料が0円になっている。単元未満株は儲からないと言われてはいるが、元本が少ない人でも、初心者でも長期的に買い増しができ、リスクも単元株で購入するよりも少ないのでお勧め。自分もワン株を中心に投資をしているが、それなりにプラスにはなっている。すぐに大きく儲けようと思わなければ購入手数料0円はかなり魅力的だと思う。
マネックス証券を利用しています。他の証券会社を試したことがないので、正確な比較はできませんが、手数料は他の証券会社の方が低いところがあるようです。しかしながら、銘柄分析ツール(マネックス銘柄スカウター)はかなり使いやすく重宝しています。この分析ツールは国内株だけでなく、アメリカ株、中国株に関してもあるので、米国株や中国株を買いに行くときにも利用できるので、大変助かっています。また、アナリストのレポートなども閲覧できるので、私個人としてはかなり使いやすい証券会社かなと思っています。
マネックス証券の良い点として、アプリはとても使いやすいと思います。まず。保有資産、損益などをグラフで表示し、次に投資した方がいいものをアドバイスしてくれます。また、アプリ上から投資に役立つ情報を見ることができ、とても勉強になります。
次にマネックス証券の悪い点は、入金、出金がしにくいところで、時間がかかります。即時入金を望む人はお勧めしません。あと、外国株はマネックス証券の別アプリを用意しないといけないのも難点だと思います。
SBIネオトレード証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.9点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:15件
■一番の利点は、資金だけでなく、Tポイントが使えるということ
Tポイントは毎月200円手数料で引かれるが、同じ200Tポイントとして付与されるので実質0円で投資をし続けられるのが、最も気に入っている点です。
■最も不便な点は、単元未満株(100株に満たない時)は、指し値注文ができないということ
単元未満株は、指し値注文ができないです。その為、前場もしくば後場での成り行きでしか注文することができません。
私は、高配当株銘柄投資家です。つまりリストアップした目ぼしい銘柄の株価が下がった時に買い付ける。そしてよっぽどの不祥事・業績悪化が起こらないと売却しません。
私のような、長期でコツコツと積み上げていくタイプの投資家さんに向けては、最適だと思います。単元未満株の指し値注文はできませんが、基本売らないので、大体の安値で購入できれば、大した問題にならないのではないでしょうか。
国内大手の1株から購入可能でバリュエーション豊かな銘柄種類と、手数料が低い、ティポイント、配当も受けられるなどの特徴があるで投資初心者も始めやすいと思います。売買手数料は無料な反面、毎月220円コストかかる(ティポイントで同額を還元されますが)ので、目的によってはあえて利用する必要はないかもしれません。
売買時の価格が分かりにくいので、その点はマイナスですね。
高配当銘柄目的なら、あまりお勧めはしません。
手軽に始められてよい。アプリの画面も見やすい。個別銘柄の検索も、比較的探しやすい。特に株主優待が受けれる銘柄を検索できることは便利だ。しかし、操作をしていると、すぐにブラウザへ遷移することが難点。あまりアプリの意味がないのではないか。できるだけアプリ内で完結するようにしてほしい。Tポイントを使って投資できるのはいいが、そもそも貯まっているポイント数が低すぎて、投資で使おうと思わない。本当に投資初心者で数千~数万円ぐらいの取引しかしない人にはちょうどいいかもしれない。
主に国内高配当株投資のために利用しています。1株単位で国内株式が購入できるので資金が少ない私にとっては分散投資をした私には好都合でした。外国株式も同時に購入したかったので私はSBI証券とSBIネオモバイル証券を同時に開設し投資をしています。SBIネオモバイル証券は毎月の手数料はかかりますが、Tポイントで還元されるのでコストを抑えたい方には特におすすめです。発注の時間帯によって約定価格が異なる点と、成行注文しかできな点は注意ポイントです。
SBIネオモバイル証券は日本株を毎月50万円以下で取引するのであれば取引手数料は一律の220円+投資に回せる期間限定Tポイントが200ポイントが付与されるという破格の取引コストの安さが魅力であると思います。
投資信託ではなく実際に企業株をS株単位で購入できるため、大きな資金はないがゆくゆくはある企業の優待を受けたい等の取引初心者の方や、日本株の高配当株式に分散投資をコツコツしていき、最終的には月換算で例えば5万円の配当金を得られるポートフォリオを作成してみたいというような長期志向の方にお勧めできる証券会社です。(取引がない月にも220円の取引手数料は取られるため、ある程度長期目的を持ち少額でも毎月取引する人が向いていると思います)
このような特徴のため大口の取引をしたい方はあまり向いていないと思います。
例えば次の50万超から300万以下は月で1100円の取引手数料がかかってきます。300万を月に取引する方はおそらく初心者や長期目線での取引の方では少ないと思いますので他の証券会社を利用したほうが結果的に手数料が安くなるのではないかと思います。
また日本株式のみですので、他の新興国などに投資したい方は最初から対象外となります。
ツールに関しては他の証券会社と比較するとあまり機能は揃っていないと感じますが個人的にツールノウハウがあるわけではないのであくまで主観的な感想です。また長期目線の方や初心者の方にはツールの豊富さや使い勝手はさほど影響のないと感じてもいます。これも主観です(笑)
auカブコム証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
6.4点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:9件
auユーザーにとっては比較的に簡単に始められる証券会社だと思います。じぶん銀行口座を持っていれば入出金の手数料も無料です。又、投資資金としてpontaポイントも使用出来る為、ポイントの有効活用にも繋がります。半面、パソコンから操作する場合は情報も解りやすく簡単に操作が出来ますが、スマートフォンからの場合、アプリの情報だけでは判断する情報が乏しく、使いづらいと感じています。今後、積み立てNISA等の投資信託も初めてみたいと思います。
auカブコム証券はプチ株があるから分散投資ができることが最大の強みだと感じました。大学生や資金のあまりない方でも株式投資を開始できることはかなり良いことだと思います。もちろんNISA口座も作ることができる為、税金面もばっちりですね。少し残念な点としてはSBIなどに比べてホーム画面が少しわかりづらいと思いました。イメージ的にはごちゃごちゃしていてどこに入金、出金などがあるかわわかりづらくそこはSBIに負けていると感じました。また初回設定のパスワードも郵送だったのでHTMLファイルで送ってほしい。また郵送である分口座開設から取引開始まで少し時間がかかった印象です。とは言っても総合評価は良いと思います。
数多くある証券会社の中から、カブコムを選んだのは、使い勝手が良いことに加えて、情報収集も早くて参考にできるからです。これまでにも、私自身、証券会社を使った経験がありますが、ここまで高品質なところはありませんでした。
カブコムの良さは、取引のしやすさもあると思います。昔のように、証券会社の担当者を介することなく、注文が可能です。私が特に気に入っているのは、ただ単に有望銘柄などの紹介に終わることなく、具体的な買い時売り時のアドバイスもしてくれることです。
全くの初心者から始めました。ビギナーズラックか、適当に買っていてもそこそこの利益がでたのです。当時のカブドットコムでの売買が容易で使いやすかった影響もあると思います。チャート画面が非常に見やすく売買に集中できたのです。この点はauカブコムに変わってから更に磨きがかかったと思います。しかし、所詮は勉強不足の初心者、やがて損益は拡大し、売り時の決心がつかぬまま塩漬けにする株も増えてしまいました。暫くは売買も自制しシミュレート売買のみで勉強を続けたこともありました。現在も継続できているのは、やはりインターフェースの良さ、使っていて楽しい、ストレスを感じないからだと思います。株を始めるにも、深く関わるにも、auカブコムは最適ではないでしょうか。
おおきな特徴としてあげられるのは多彩な注文方法だと思います。
注文方法は指値や逆指値、成行注文が代表的で多くの証券会社がこの3つのみとなっていますが、カブドットコム証券はWターン、トレーディングストップ、時間指定など多くあります。
これら特殊注文の多くは自動で発注や取り消しなどをしてくれるため、日中の取引が始まる前などに注文予約をして置くことができ、日中仕事で株価を見ることができない私にとってはとてもありがたいシステムになっています。
またFXにおいても自動売買のシストレFXがあるなど充実しており忙しい方におすすめです。
LINE証券/株式投資の評判・口コミ
口コミ総合評価
7.7点
総合評価(10点満点)
最新口コミ 口コミ投稿数:35件
楽天証券は楽天銀行との連携で入金や出金がスムーズで、画面の見やすく操作が容易な点がオススメ。楽天証券の利用で楽天市場でのポイント倍率が上がったり、その他楽天サービスでの特典やキャンペーンにも影響があるため、楽天経済圏の方は利用する価値が大いにあります。また、楽天ポイントで投資信託の投資が可能で少額でリスクなく投資できる環境で、国内株式はもちろん米国株式や債券、為替等金融商品が充実しているため初心者からでも始めやすいです。
楽天証券は利用することによってポイントが貯まっていくので贔屓にしています。それ以外にも投資信託の銘柄数も非常に多く、特にアメリカを始めとする海外に投資したいときにはとても便利です。私は日本株以外にも海外の株式にも投資を行っていて、こちらを利用することで上手にポートフォリオを作ることができています。さらにグループ会社の楽天銀行の口座を開設しておくと、資金の移動も簡単にすることができます。楽天ポイントを貯めている人や、これから投資を始めようと考えている人にとって使いやすい証券会社としてお勧めです。
トレードツールの「マーケットスピード」が使いやすいです。業界別指数一覧やヒートマップなど、直感的にマーケットの状況が把握できる機能が特に優れていると思います。また、楽天証券のメディア「トウシル」は情報の質・量ともにレベルが高く、投資の初心者からベテランの方まで幅広くカバーする内容になっています。楽天証券独自のサービス(「楽ラップ」や投資信託など)を無理に薦める内容は見受けられず、中立的な立場からの分析・アドバイスになっている点も安心して利用できるポイントかと思います。
私が株式投資を始める際にはどこの証券会社がよいか全く知識がなかったので、当時口座開設のキャンペーンをしていた楽天証券を選択しました。同時に楽天銀行の口座を開設し、数千ポイントがもらえたと記憶しています。またわずかなことではありますが、楽天カード、楽天銀行と提携しているので振り込み手数料や金利などの優遇があります。取扱銘柄は国内は希望するものは全て買えましたが、米国などの企業で買えない銘柄がちょくちょくあります。
銘柄数も多く、最新の流行りの商品といったものは導入も早く銘柄選択には困りません。メンテナンスが定期的に入っており、今までバグなどに出くわした事がないのも信頼ができます。
デメリットと感じているのは、米国株を取引している時に、メンテナンス時間が被ってしまい取引が出来なくなるタイミングがよくある事や、一部分だけスマートフォンに対応していなくスマートフォンで利用しているといきなりPC画面に飛んでしまったり操作がやりづらい事があります。
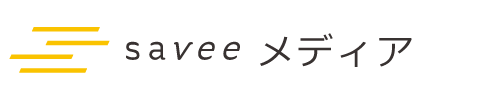




最新口コミ 口コミ投稿数:80件
株に対して知識がない私が株を始めたきっかけは、ネット証券というものが出来てゲーム感覚で始められると思ったからです。まだネット証券は数社しかなかった頃、一番手数料が安かったイー・トレード証券、現SBI証券を選びました。デイトレーダーが、数分間でいくら儲けたとか、そんなことが話題になった時代です。SBI証券は一ヶ月間、1度でも取引があればトレーディングツールを無料で使うことが出来たので、それもデイトレードするのには最適な環境でした。HYPER SBI というトレーディングツールですが使いやすいです。また、住信SBIネット銀行の口座があれば、銀行の振込手数料が無料になるのがとてもお得です。
はっきり言ってしまって、特にこれが大きな特徴というトレード上のメリットとかがあるわけではないのですがIPOに関しては抽選に落ちてもポイントがもらえて物凄くたくさん貯めないといけないのですが、それによって優先権をもらえるというのはよいですね。サポートとかそもそもあんまり問い合わせたことがないのでわかりませんが、悪くはないとは思います。SBIネット銀行と紐づけさせることができるのがとても便利ではあります。
初めて開設した証券会社の口座でした。優待目的でオリックスやスカイラークの株を持っていました。
また米国株の投資信託をクレジットカード決済で購入しておりかなりお得です。
サービスの改悪が続いている証券会社もある中、SBI証券はサービスの向上を続けており、今後もメインバンクとして何十年と渡って使用していきたいと思っています。
IPO投資も行っており、SBI証券はIPOの抽選に外れるとポイントが貯まりいずれは当選することができるので、他社にはない強みだと思います。そのせいもあり、昔から一番よく使う証券会社です。
SBI銀行口座も開設することでお金の移動がスムーズにでき、引き下ろす際も手数料無料だったりかなり便利に使えました。
国内現物取引の手数料は業界最安値で他の追随を許さない。中長期取引もデイトレードにとってもやりやすい料金体系で、初心者も安心して利用できる。専用の取引ツールを使用せずとも公式ページの株式売買がシンプルで利用しやすい。わからないところがあればカスタマーサポートに電話すればすぐに繋がりやすくて親切なのも、業界最大手だけに余裕がある対応だと思う。少し残念なのは、取引の参考になる情報量がかなり少ないこと。口座を開設して10年を超えるが、メールをもらったのは数えるほどしかない。
口座開設、維持手数料が無料だったので口座を開設した。コストが安いことはもちろんのこと海外のETFや個別株もたくさん取引できるので、自分の思い通りにポートフォリオが作れる。また、時々キャンペーンでちょっとした投資資金をもらえるのも嬉しい。さらに、投資信託を保有することでTポイントやVポイントを貰えるプログラムもやっている。SBI証券と同様の楽天証券でも保有する投資信託に応じて楽天ポイントがもらえるが、SBI証券の方が還元率が良い。以上の点がSBI証券の長所だと考える。