なぜ、住民税を滞納するのか

どんな税金であっても、支払う義務が生じているのであれば、払わなくてはいけません。それにも関わらず、延滞・滞納をしてしまいがちなものの1つが住民税です。今回の記事では
- なぜ、住民税を滞納するのか
- 住民税を滞納するリスク
- 住民税の滞納で手遅れになる前に自分でできる対策
という観点から、住民税について詳しく話しましょう。
住民税の基本

住民税とは、都道府県・市区町村に支払う税金の1つです。教育・福祉、行政サービスを行うための資金として徴収されると考えましょう。
住民税は収入によって額が違うのはもちろん、どこに住んでいるかによっても違うのが大きな特徴です。

どの都道府県・市区町村に対して住民税を支払うかは「その年の1月1日現在の住所」を基準に決まります。
→2020年6月から2023年5月までは東京都北区に、2023年6月以降は埼玉県さいたま市に納める。
また、住民税の金額の決まり方ですが、所得(給料、収入)にかかわらず一定である「均等割」と所得に応じてかかる「所得割」の2つを足した額になります。
| 所得割 | 市町村民税(%)+都道府県民税(%)が前年の所得金額に対して課税される |
|---|---|
| 均等割 | 市町村民税+都道府県民税が一定額として課税される |
普通徴収と特別徴収


上のやり取りにもあるように、会社勤めをしている人=給与所得者の場合、住民税があらかじめ給与から天引きされていることから、特に住民税を納める手続きをしたことがない人がほとんどかもしれません。
住民税の納付の仕方には、普通徴収と特別徴収があります。
| 普通徴収 | 市区町村から送付される納税通知書を使い、年4回(6月、8月、10月、1月)にわけて納税義務者本人が納税する方法。 |
|---|---|
| 特別徴収 | 事業主(給与支払者=会社のこと)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月天引きし、これを納税義務者に代わって納める方法。 |
事業主に対しては、多くの都道府県で特別徴収を行うことが義務化されています。つまり、会社勤めをしている限りは、ほとんどの場合において会社が住民税を天引きし、自分の代わりに納めてくれているはずなので、よほどのことがなければ、住民税は延滞・滞納しないでしょう。
また、普通徴収の場合も、口座引き落としにしたり、クレジットカードで納付したりなどして、忘れないようにすることができるはずです。
独立起業した、再就職活動をしている人は特に注意
注意すべきなのは、その年度の途中で会社を辞めて独立起業したり、再就職活動をしたりしている人のケースでしょう。会社勤めをしている限りは、住民税は給料から天引きされているため、特に気にする必要はありません。しかし、会社を辞めてしまった場合は天引きができなくなるので、それ以降の住民税は自分で納付書を使って払わなくてはいけないのです。
例えば、その年の12月に退職した場合は
- 6月から12月までの市町村民税、都道府県民税:給料から天引きされている
- 翌年1月から翌年5月までの市町村民税、都道府県民税:自分で納付書を使って払う
という扱いになります。ただし
- 退職後、他の会社に就職し、そこで残りの市民税・県民税を給与から天引きする
- 残りの市民税・県民税を、退職金などから一括して徴収した
などの対応がとられることもあるので、前の会社を辞める際や、新しく就職した会社に出社した際に確認してみるといいでしょう。

前年から売上が激減したフリーランスの人も注意
住民税は、前の年の1月から12月までの収入をもとにして、翌年の6月から支払う金額が算定されます。ある年の収入が多かったからといって、使いすぎてしまうと、翌年以降の住民税の納税資金が確保できない恐れもあることに注意してください。
わかりやすくするために、かなり極端な例を考えてみましょう。
→このようなケースであっても、翌年の6月からは年収3,000万円として計算した金額で住民税を支払わないといけない。
詳しくは後述しますが、住民税を延滞・滞納するとかなり重いペナルティが課されるので注意してください。
住民税を滞納した人の末路は悲惨


実際に、住民税を滞納したらどうなるのか、一般的な流れをまとめました。
↓
督促状・催告書が送付される
↓
それでも納付がない場合は、本人の承諾なしに財産調査が行われる
↓
滞納処分=給料、不動産などの差押えが行われる
↓
それでも完納にならない場合は、差押えた財産の換価公売(売ってお金に換えて、税金への支払いに充てること)が行われる

住民税を滞納する3つのリスク

次に、住民税を滞納する3つのリスクとして
- 不動産、給与、預貯金などの差押えが行われる
- 延滞金が課される
- 仕事上の信頼をなくす
を解説しましょう。
1.不動産、給与、預貯金などの差押えが行われる
既に触れた通り、住民税を延滞・滞納した場合、本来の納期限から20日経つと、督促状が送られてきます。

督促状を受取っても延滞・滞納している場合は、電話がかかってきたり、担当者が家に訪ねてきたりします(催告)。
督促状の送付や催告があっても、延滞・滞納を続けていた場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。つまり
- 支払い予定の給料や売掛金
- 本人名義の預貯金、不動産、動産、自動車
などがあるかを調べ、差し押さえるものがないか調べるということです。状況によっては、滞納している本人はもちろん、家族や取引先などにも調査が入ることがあるのに注意が必要です。
一人暮らししてる兄貴が住民税15万滞納してるって電話がうちに来て笑った
— きど (@kidodoooo) September 3, 2015


なお、財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
この財産調査を経て、差し押さえる財産を決定し、実際に差押えを行います。

- 不動産の場合は登記簿上に「差押」と記載される上に、登記簿上の権利者に「差押え通知書」が発送される。売買、贈与、棄損、破棄はできない。
- 給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付する。
などの対応がとられると考えましょう。

また、不動産(家、土地など)を差し押さえた後も、なお延滞・滞納が続いている場合、最終的に公売を行って換価し、延滞・滞納した住民税の支払いに充てられる点に注意が必要です。



2.延滞金が課される
また、他の税金やクレジットカード、ローンの支払いなどと同じように、延滞・滞納した場合は、延滞・滞納した期間に応じて延滞金が課されます。具体的な延滞金の割合は市区町村によっても異なるので、事前に確認しましょう。
例えば、埼玉県さいたま市の場合、住民税を延滞した場合の延滞金は以下のように定められています。
| 延滞・滞納した期間 | 平成12年1月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日以降 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% |
| 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 年14.6% | 特例基準割合+7.3% |

特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。ちなみに、平成30(2018)年1月1日から令和2(2020)年12月31日までは年1.6%になっています。
3.仕事上の信頼をなくす
既にふれた通り、督促状が送られてきたり、催告(電話連絡や訪問)があったりしたとしても住民税の延滞・滞納をしていた場合、財産調査が行われます。つまり、自分が勤めている、経営している会社はもちろん、取引先にも電話がかかってきたり、担当者が訪ねてきたりして、聞き込みが行われるわけです。取引先側からすると
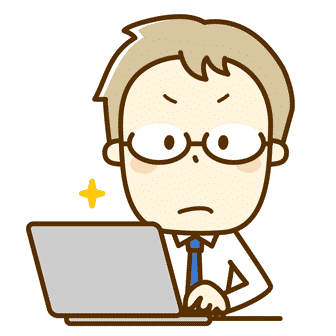
と不信感を抱くでしょう。当然、その不信感が取引の停止につながることにも注意しましょう。
<取引先に調査、契約打ち切り> 別の横浜市の男性は数年前から事業が振るわず、市税(個人住民税)や国民健康保険料を滞納していた。
男性は何とかお金を工面して納めると訴えたが、市の担当者は取引先が男性に支払う予定の売掛金を差し押さえようとした。 #引用— しんいち🐽 (@amr_shin) September 4, 2015
住民税の滞納で手遅れになる前に自分でできる対策

最後に、住民税の滞納で手遅れになる前に自分でできる対策として
- 督促状が届いてから1週間に役所に問いあわせる
- 話し合いをしに役所に出向く
- 現在のお金の使い方を見直す
- 借金がある場合は、債務整理を検討する
- 納税の猶予、換価の猶予をしてもらう
の5つについて解説しましょう。
1.督促状が届いてから1週間以内に役所に問いあわせる
日本の法律では、督促状を発送した日から数えて10日以上たっても、住民税が延滞・滞納されたままだったら、財産の差押えをしないといけない決まりになっています。
地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき
裏を返せば、督促状が届いてから1週間以内であれば、交渉の余地はあるということです。
2.話し合いをしに役所に出向く
督促状が届いてから1週間以内に住民税が払えそうにない場合は、話し合いをしに自宅を管轄する市区町村役場に出向きましょう。「住民税の件で相談しにきました」といえば、適切な窓口を案内してくれるはずです。その際、担当者からいろいろと質問されるので、嘘をついたり、ごまかしたりせず、現状をありのままに伝えましょう。
また「本当に住民税が支払えそうにない」ことがわかるよう、資料はできる限りそろえていきましょう。例えば、次のものが当てはまります。
| 資料 | 具体例、補足事項 |
|---|---|
| 財産目録 | 市区町村によって様式が用意されていることが多い |
| 世帯の収入がわかる資料 | 直近3か月の給与明細、預貯金の記録、受給者証、帳簿等で収入が確認できるもの |
| 世帯の支出がわかる資料 | 家賃振込証、賃貸借契約書、住宅ローンの契約書等 国民健康保険料がわかるもの 交通費がわかるもの(定期券のコピー、または通勤経路・日数と金額を書いたメモ等) 医療費、介護費用等がわかるもの(領収書のコピー等) 借入金の残債額と月々の返済額がわかるもの(領収書、契約書等) その他、生命保険料等、毎月 11万円以上の支出があれば、その内容と金額、相手がわかるもの |
| 世帯の蓄えがわかる資料 | 預貯金(20 万円以上あるときは、口座・名義人と残高がわかる資料) 株式等(証券会社、口座・名義人、保有株式等の種類、数量がわかる資料) 生命保険(保険会社名と証券番号等、契約者名がわかる資料) 仮想通貨(取り扱い機関、口座等・名義人、保有財産の種類・数量等がわかる資料) その他、蓄えがあればその資料 |

話し合いの結果
- 分割納付(何回かに分けて支払う)
- 減免(支払額を減らしてもらう)
などの対応をしてくれることもあります。
住民税払ってきたよ…😂😂
まぁ、一昨年とかは、住民税や年金ほんとうに払えなくて滞納しまくって、役所から催促きて、細かい分割とかにしてもらったり、何度も役所に電話したり足を運んだりしていました… pic.twitter.com/typPgY219E
— 金遣い荒デブ子@汚部屋住人→断捨離中 (@kanebububu) August 31, 2020
3.現在のお金の使い方を見直す
住民税が払えないほどになっているということは、現在のお金の使い方にもなんらかの問題点を抱えている可能性があります。
- 保険の見直しをする
- 携帯電話を格安スマホにする
- 使っていない月額プログラムなどは解約する
- 家計簿をつける
など、無駄遣いをしていないかどうかをしっかりチェックしましょう。
4.借金がある場合は債務整理を検討する
住民税の支払い自体は、たとえ自己破産をしたとしても、免除されることはありません。生活保護に該当するなど、特殊なケースの場合は減免が受けられることもありますが、基本的には請求された金額を支払うもの、と考えましょう。
しかし、他の支払いを減らすことができれば、その分住民税の支払いに回す余裕が出てくるはずです。クレジットカードやローンの返済が滞っているときは、債務整理も視野にいれましょう。
一般的な債務整理の方法としては
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
が挙げられます。それぞれについて、わかりやすく表にまとめました。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減額率 | 基本的に利息のみが減額される | 大きく減額される | 基本的に全額免除(ただし税金は支払う必要あり) |
| 財産がなくなるか | なくならない | ローンの残債がある車はなくなる(担保として没収される) | 生活に必要な最低限の財産しか残せない |
| 官報への掲載 | ない | あり | あり |
| 仕事への影響 | ない | ない | 一部の仕事が制限される |
どの方法で債務整理を行なえばいいのかは、その人の職業や借金の状況によっても結論は異なります。弁護士や司法書士などにまずは相談しましょう。
5.納税の猶予、換価の猶予をしてもらう
「今は払えないけど、将来的に払える見込みがある」という場合は、納税の猶予や換価の猶予を検討してもいいでしょう。
まず、納税の猶予とは、わかりやすくいうと「税金の支払いを待ってもらうこと」です。相応の事情があって、住民税を期限内に納付できない場合は、市区町村に対して申請を行うと、所定の期間(1年以内の場合が多い)、納付を待ってもらえます。
具体的には、次のケースがあてまると考えましょう。
- 災害や盗難にあったことが原因で、財産が大幅に滅失したとき
- 納税者やその生計を一にする親族が病気にかかり,または負傷したとき
- 事業を廃止、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
一方、換価の猶予とは差し押さえを受けた財産の換価(=売ってお金に換えること)を待ってもらうことです。こちらも、申請を行うことで、所定の期間(1年以内の場合が多い)、換価を待ってもらえます。


