目次
なぜ相続は争族になってしまうのか

家族の誰かが亡くなった場合、避けて通れないのが相続です。つまり、その人が住んでいた家や持っていた株、現金などの財産を、遺された家族で分け合って引き継ぐことですが、この相続を原因として、トラブルが起こることもありえます。

そこで、そもそもなぜ相続が争族になりがちなのか、考えてみましょう。理由として
- お金のからむことだから
- それにも関わらず対策が手薄になりがちだから
- タイムリミットがかなり短いから
の3点を解説します。
1.お金のからむことだから
当たり前かもしれませんが、相続はいわば「遺してくれた財産を山分けすること」です。そうなると、ほとんどの人が「あわよくば自分の取り分が多くなるようにしたい」と考えるでしょう。そうなると、好き勝手なことを言い出しがちです。たとえば

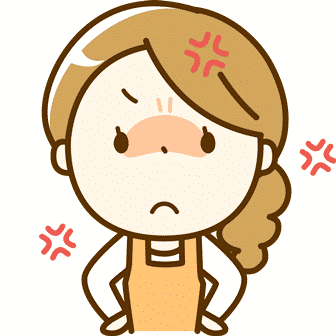
などが言い分として考えられます。お互いが上手に譲歩し、妥協点を見いだせればそこまで深刻に考える必要はありません。しかし、うまく話し合いがまとまらないので、弁護士に依頼して裁判を起こす、という展開も十分に考えられるでしょう。

2.それにも関わらず対策が手薄になりがちだから


やり取りにもあるように、相続を争族にしないためには、生前から話し合うことが非常に大事です。特に、2015年に相続税法が改正され、基礎控除額が大幅に引き下げられました。つまり、相続税を支払わなくてはいけない人の範囲が増えたのです。それにも関わらず、相続について生前に話し合う人はそう多くないのでしょう。
日本財団が2017年に行ったアンケートでは親世代の立場からは「自身の財産の相続について」、子世代の立場からは「親の財産について」の話し合いの状況に関する設問が設けられていました。結果を表にまとめたのでみてみましょう。
| 項目 | 自身の財産の相続について(n=1,717) | 親の財産について(n=909) |
|---|---|---|
| 既に話し合いを終えている | 11.8% | 6.4% |
| 現在話し合っている | 7.1% | 4.7% |
| 話し合いたいが、まだ話し終えていない | 27.8% | 28.5% |
| 話し合いもしておらず、必要性も感じていない | 53.3% | 60.4% |
では、なぜ話し合いができていないのかについてもデータを見ておきましょう。こちらも表にまとめておきました。
| 項目 | 親世代(60歳以上)(n=1,393) | 子世代(59歳以下)(n=808) |
|---|---|---|
| まだ死ぬと思っていないから/まだ元気そうだから | 26.1% | 33.0% |
| 話し合うほどの財産がないから | 51.8% | 32.7% |
| 相続内容の整理がまだできていないから/どんなことを話し合うべきかよくわからないから | 15.2% | 23.3% |
| 縁起が悪いから | 2.4% | 14.7% |
| 生きている間の関係がおかしくなりそうだから | 3.7% | 10.6% |
最も多かった選択肢が「話し合うほどの財産がないから」でした。では、本当に話し合うほどの財産がなければ、争族にはならないのでしょうか?
金持ちケンカせず、は本当だった
実際は真逆で、相続財産が少ないほど、もめることが多いという話にも触れておきましょう。
裁判所は毎年「司法統計」といって、日本国内で1年間に開かれた裁判に関する数値データを集計し、公開しています。その中で「相続に絡んで起こされた裁判の数」が集計されているので、表にまとめました。
| 遺産の価額 | 裁判の件数(件) | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2448 | 33.9% |
| 5,000万円以下 | 3097 | 42.9% |
| 1億円以下 | 780 | 10.8% |
| 5億円以下 | 490 | 6.8% |
| 5億円超 | 42 | 0.6% |
| 算定不能・不詳 | 367 | 5.1% |
出典:令和元年度司法統計「52 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く) 遺産の内容別遺産の価額別 全家庭裁判所」
相続にからんで起こされた裁判のうち、7割以上が遺産の価額が5,000万円以下だったということです。逆に、遺産が1億円を超える相続の場合
- もともと、資産家である
- 自営業を営む家であるなどの理由で、事業承継も含めて話し合いをしていた
などの理由から、生前に税理士や弁護士などの専門家に相談し、対策を練っていたことが考えられます。
「金持ちケンカせず」という言葉があります。本来は「金持ち=資産家は金銭的にも、心理的にも余裕があるため、周囲との争いをしない」という意味です。しかし、相続においても、生前に十分な対策を講じているため、金持ち=資産家の相続は争族になりにくいのでしょう。
生前に認知症になった場合も難航する
自分自身が「まだ死ぬと思っていない」、家族が「まだ元気そう」と思っていたとしても、明日になればどうなっているかはわかりません。急病で万が一のことになったり、認知症などの病気になったりして正常な判断能力がなくなってしまうこともあり得ます。
特に、認知症などの病気で「本人の意思確認ができない」と判断された場合、不動産などの財産の処分(売ったり、誰かにあげたりすること)が自由にできなくなります。
当然、こんな状態では相続の話も難航することは、知識の1つとして覚えておきましょう。

3.タイムリミットがかなり短いから
経験がある人も多いはずですが、誰かが亡くなってしまうと、遺族はしばらくの間、対応に追われます。その間を縫って相続の手続きもしていかないといけないので、かなりハードなスケジュールをこなさないといけません。

| 被相続人の死亡 | 相続の開始 通夜・葬式、初七日の法要、四十九日の法要 ※この間に、被相続人の財産・債務・遺言書の有無を確認する |
|---|---|
| 3カ月以内 | 相続の放棄または限定承認 ※相続人の確認を行う |
| 4カ月以内 | 被相続人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告) |
| 10カ月以内 | 相続税申告書の提出・納付 |
こちらのスケジュールからもわかるように、3カ月である程度の方針を固めて、10カ月以内には相続税としていくら払わなくてはいけないかを計算し、実際に納めなくてはいけません。



相続を争族にしないためにやるべきことは?
結局のところ、相続が争族になる=もめてしまう原因は
- お金がからむことから、そもそももめてしまいがちな話題である
- それにも関わらず、生前から準備していない
- しかも期限通りに手続きを進めないといけないので精神的な余裕がなくなる
の3点です。実際に手続きをするのは亡くなった後になりますが、それでも、生前から
- 家族はどうしたいのかを知っておき、形に残してもらう
- 相続税の基本的な仕組みを知り、自分たちの場合は払う必要があるのかを把握する
ことで、ずいぶんと負担は減るでしょう。そこで、具体的にやっておくべきこととして
- 親との話し合いをする
- エンディングノートを書いてもらう
- 相続する資産について現状把握する
- 遺言書を準備してもらう
- 相続の基本的な仕組みについて知る
の5つについて解説しましょう。
やるべきこと1.親との話し合いをする

最初にやるべきことは「親との話し合いをすること」です。
親=被相続人の気持ちに寄り添うことが大事

というように、家族からのネガティブな反応を恐れて話し合いができない人もいるかもしれません。相手があきらかに好ましくない反応をしているのに、強引に話を進めるのは止めましょう。やはり、相続は「亡くなった後の話」である以上、生前にそのような話をするのは好ましくない、と考えている人も一定数います。
もし、切り出し方がわからなければ「身近な人が相続でもめて大変だったみたい。うちは大丈夫かな?」など、あくまで「自分や家族のことを心配している」という気持ちを表に出したほうが話しやすいはずです。
生前にしか相続の話はできない

亡くなった後に自身の意思を伝える方法は「生前に書面を残しておく」以外ありません。家族の反応を見ながら話すのは、生きているうちにしかできないことです。
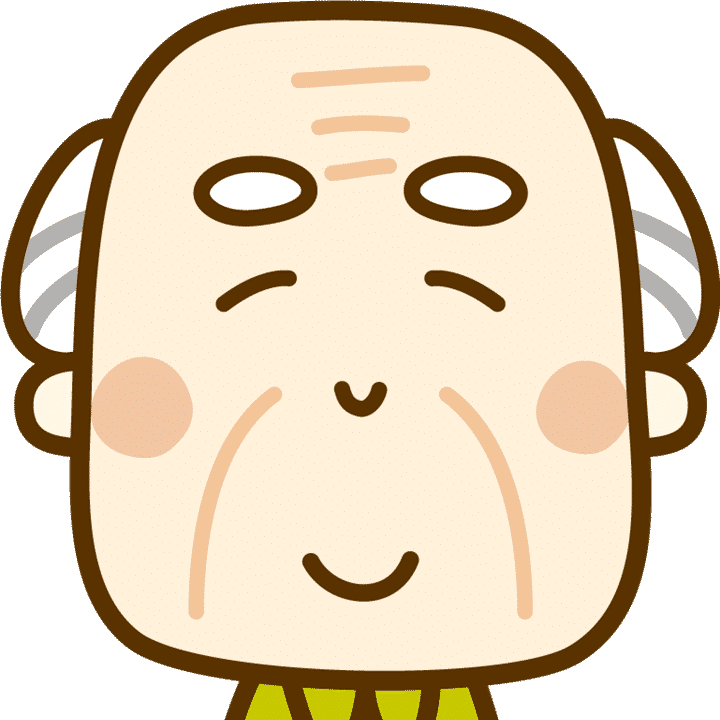
と思っていたとしても、お金が絡むことだけに、何がきっかけで争いに発展するかはまったくわからないのです。どんなに仲がいい家族だったとしても、相続でもめたことがきっかけで、その後のやり取りがぱったりと途絶えてしまうのも珍しくありません。
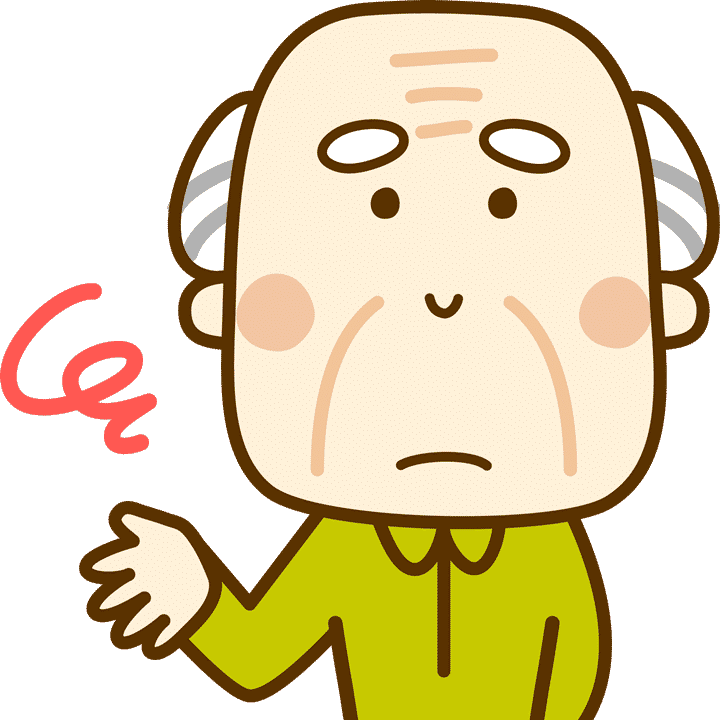
と思うなら、まずは生前から話し合うことを大事にしましょう。
やるべきこと2.エンディングノートを書いてもらう
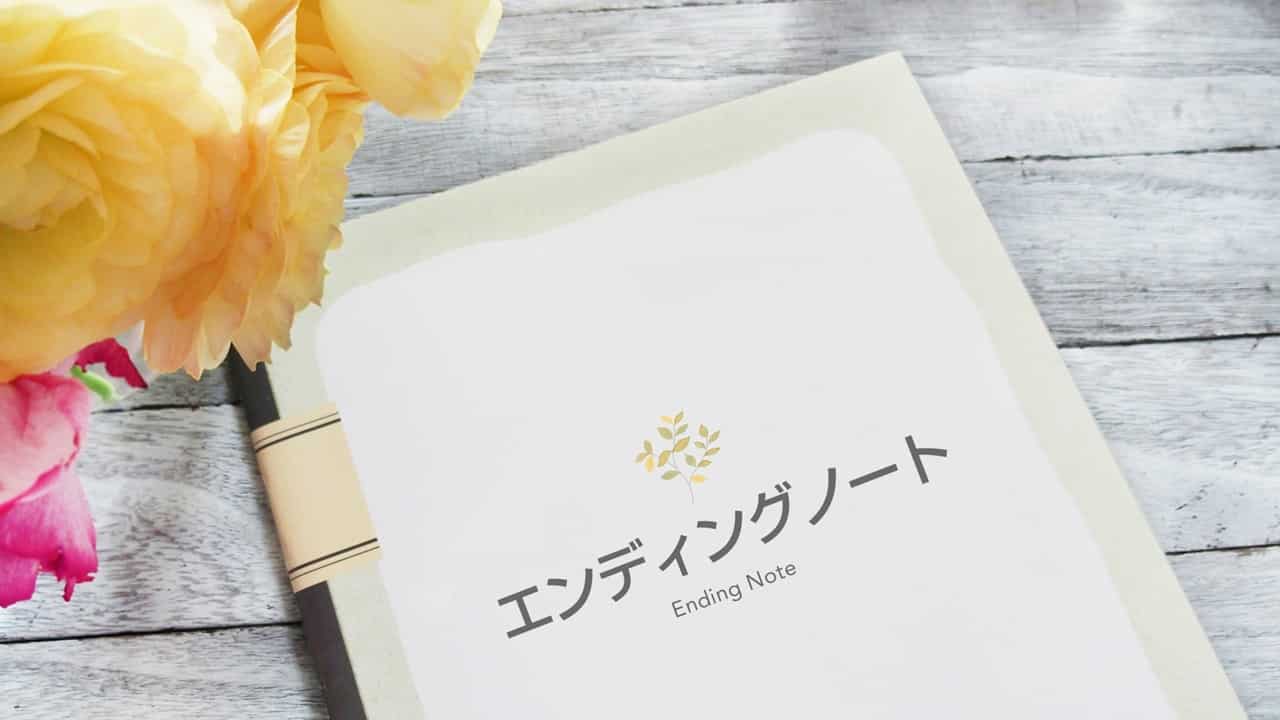
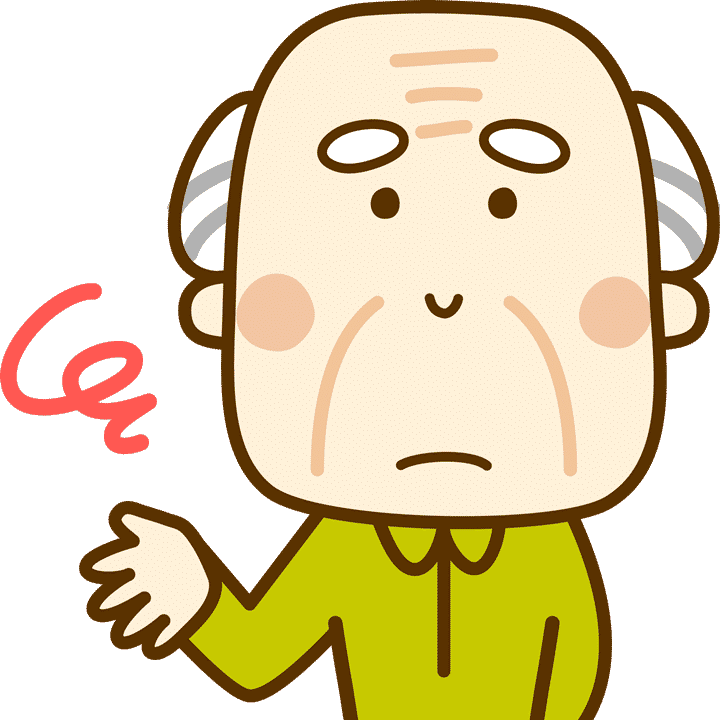
と思うなら、エンディングノートを用意してもらいましょう。
何かあったときの対応がずっと楽になる
エンディングノートとは
- 自身の人生の振り返り
- 所有している財産の補完場所
- 葬儀の方法や知り合いの連絡先
- 家族への感謝の言葉
などを書き記すことができるノートです。遺言のように法的な拘束力はありませんが、万が一のことがあったとき、家族がどのように動けばいいか決める際に非常に参考になります。

やるべきこと3.相続する資産について現状把握する

離れて暮らしている場合はもちろん、一緒に暮らしている場合であっても、家族がどれだけの財産を持っているかを正確に把握している人は少ないかもしれません。しかし、相続に当たっては「亡くなった家族=被相続人がどれだけの財産を持っていたか」を確定するのが非常に重要になります。
どこに保管しているかは確認しよう
- 預金・貯金通帳
- 土地・建物の権利書
- 保険証書
など、資産価値があるものに関連する書類を、家族がどこに保管しているのかは、大まかでいいので把握しておきましょう。整理整頓が得意な家族なら「ああ、あのあたりにあるはず」と見当もつけられますが、そうでないなら皆目見当もつかないはずです。
ネットバンク、ネット証券の口座がある場合は要注意
また、近年はネットバンクやネット証券など、インターネット上で取引を行うため、紙の通帳や証書が発行されない金融機関も増えてきました。これらの金融機関の場合、所定のWebページにログインしないと残高がいくらなのかは全くわかりません。

- 金融機関ごとのID、パスワードを把握しておく
- そのID、パスワードで本当にログインでき、取引まで進められるのかを確認しておく
のを忘れないようにしましょう。
相続税を払うだけのお金があるかを確認しよう
相続税を含めて、税金は現金で期限通りに一括払いをするのが原則です。どうしても困難と認められる事情があれば、一部を後払いする「延納」や、株などの有価証券で代わりに支払う「物納」も選択できますが、条件が厳しくなっています。
相続税を払った後に万が一財産が出てきたらどうなる?
あまり考えたくないことですが、相続税を支払った後に、それまでは把握していなかった財産が見つかることもあり得ます。その場合は
- 改めて、遺産分割協議をやり直す
- 遺産分割協議の結果を踏まえ、修正申告を行う
という流れが、現実的な対応になります。

やるべきこと4.遺言書を準備してもらう
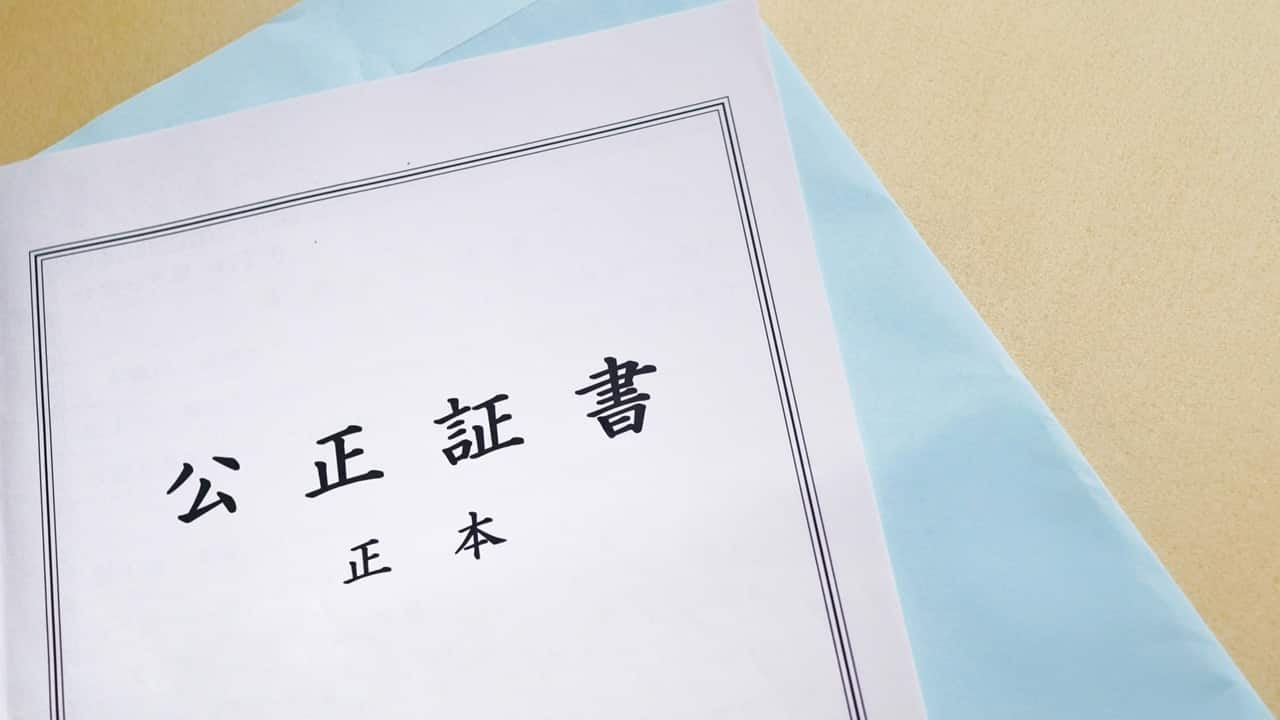
先ほど紹介したエンディングノートには、法的拘束力はありません。そのため「自分が亡くなった後、家族には必ずこうしてほしい」という意思表示をするためには、遺言書を準備してもらう必要があります。
遺言書の種類
遺言書には
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
の3つがあります。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が全文すべてを自筆で書き、押印(認印でも可能)。封筒に入れる必要はないが、代筆・ワープロ・録音は不可。 | 遺言を残したい人が公証人役場に出向き、公証人に対して話す内容を公証人が書きとる。実印、印鑑証明、身元証明書、相続人などの戸籍謄本、登記簿謄本などが必要になる、 | 遺言者が自筆、代筆、ワープロで作成。ただし、署名は自筆であることが必要。出来上がったら押印し、同じ印鑑で封印もする。その後、公証人役場に行き、自分が作成した遺言と認めてもらえば手続きが完了。 |
| 作成場所 | どこでもいい | 原則として公証人役場 | どこでもいい |
| 公証人 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 費用 | 無料 | 相続財産の額によるので要確認 | 11,000円 |
| 署名押印 | 本人 | 本人、公証人、承認 | 本人、公証人、承認 |
| 保管場所 | 遺言者が保管する | 公証役場が原本を保管する | 遺言者が保管する |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| メリット | 無料で作れる 自身の判断で書ける |
原本が公証役場で保管されるため、改ざんが起きない 無効にならない 検認手続きがいらない |
遺言は残してあることを知らせながら、内容を秘密にできる 偽造や書き換えられるリスクが低い |
| デメリット | 形式や内容の不備が原因で無効になることがある 偽造されるリスクがある 遺言書自体を見つけてもらえないことがある 検認手続きが必須 |
作成手続きが面倒 費用がかかる 証人2人を確保しないといけない |
形式や内容の不備が原因で無効になることがある 作成手続きが面倒 費用がかかる 証人2人を確保しないといけない |
遺言書は何度でも書き直せる
相続が発生する前=亡くなる前であれば、遺言書は何度でも書き直すことが可能です。その場合、前の遺言書の内容を取り消し、新しい遺言書の内容が最新のものとして扱うことが必要になります(撤回といいます)。

やるべきこと5.相続の基本的な仕組みについて知る

相続税については、別の記事で詳しく解説しますが、その前提となる知識として「相続の基本的な仕組み」について解説しておきましょう。
法定相続人とは
相続の場合、遺言書に「誰に自分の財産を相続させたいか」を書くことで、誰にでも財産を相続させることができます。

しかし、遺言書で「自分の財産を相続させたい人」を特に指定しなかった場合、法律の決まりに則って相続を進めることになります。この場合、相続人になれる人のことを「法定相続人」というので、覚えておきましょう。
誰が法定相続人になるの?
誰が法定相続人になるのかは、被相続人=亡くなった人に配偶者=夫、妻がいるかどうかで扱いが少々異なります。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合は、その他の家族の状況によって法定相続人になる人の範囲と相続分が異なります。表にまとめました。
| 相続する順位 | 相続人になる人 | 各相続人の割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
子が複数の場合は、均等に分ける。 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属(親など) | 配偶者:2/3 直系尊属/:1/3 |
直系尊属が複数の場合は、均等に分ける。 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
兄弟姉妹が複数の場合、均等に分ける。 |
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、相続順位が高い人がいるかどうかで、誰が相続人になるかが決まります。次の5つのパターンを想定しましょう。
| 配偶者なし | 子 | 親 | 自分の兄弟 | 特別縁故者 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子あり | 〇 | ― | ― | - | - |
| 子なし/親あり | - | 〇 | - | - | - |
| 子なし/親なし/兄弟あり | - | - | 〇 | - | - |
| 子なし/親なし/兄弟なし/特別縁故者あり | - | - | - | 〇 | - |
| 相続人等なし | - | - | - | - | 〇 |
特別縁故者とは、相続人が誰もいない場合に特別に財産を引きつぐとができる人です。
具体的には
- 亡くなった人と生計を同じくしていた(事実婚、同性パートナーシップで届出を出したパートナーなど)
- 亡くなった人の介護などをしていた
- 亡くなった人との特別な縁故(師弟関係、親子同然の親しい付き合いなど)があった
など、一定の条件に当てはまる人が、家庭裁判所に申し立てを行うことで認められます。
法定相続人になれないのは?

たとえ、法定相続人である家族であったとしても
- 日頃から暴力を振るわれていた
- 勝手に遺言書を偽造したり、隠したりした
など、相応の理由があれば、相続させないこともできます。

| 相続欠格 | 相続が自身に有利になるようにするために違法行為を行った相続人に対し、自動的に相続人としての地位をはく奪すること。具体的には以下の行為が当てはまる。 被相続人の生命を侵害する行為 脅迫等により遺言書が自分に有利になるよう作成・修正させる行為 遺言書の破棄・隠匿・偽造 |
|---|---|
| 相続廃除 | 相続人が日ごろから虐待や侮辱行為、その他著しい非行を被相続人に対して働いていた場合、被相続人や遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行い、相続人としての地位をはく奪すること。具体的には以下の行為が当てはまる。 日常的に暴言を吐いたり、暴力をふるっていた(いわゆるDV) ギャンブルで背負った借金を代わりに返済させていた 被相続人名義の不動産を勝手に売却した |
家族以外に相続させる、と言われたら?
原則として、遺産を誰に相続させるかは、自分の意思で自由に決められます。しかし、家族以外の人(例:内縁の妻=いわゆる「愛人」)に相続させる場合
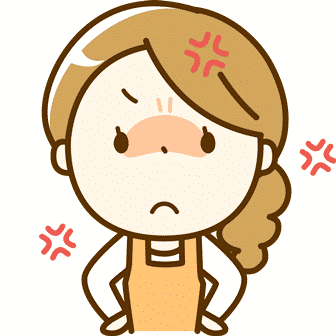
と、遺された家族の生活が害されてしまう結果にもなりかねません。そのため、法律では最低限相続できる権利として、一定の条件に当てはまる法定相続人については、遺留分を認めています。

| 相続人の組み合わせ | 遺留分 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者2/6、直系尊属1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
| 子のみ | 1/2 | 子1/2 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |


