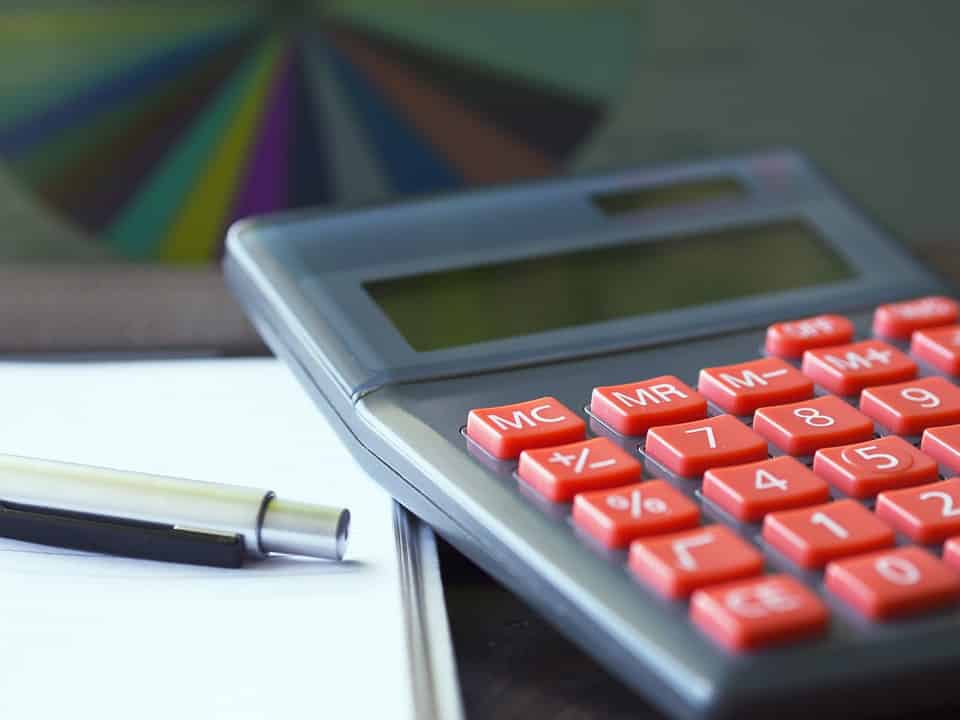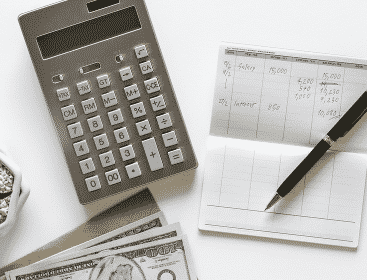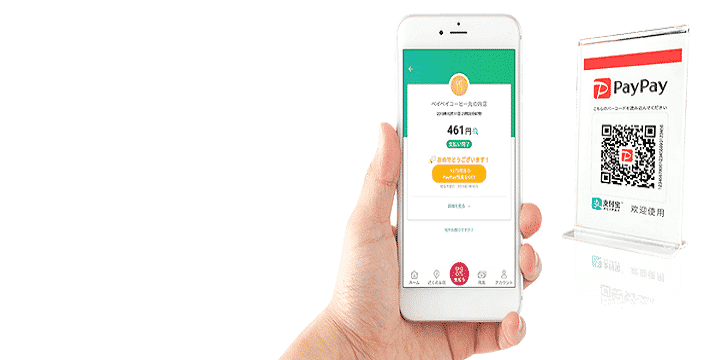目次
借金をしている、あるいは過去に借金をしていて完済した人は、テレビやラジオ・駅や電車の広告などで見る「過払い金請求」というものに興味を持っている方もいらっしゃるかもいれません。
しかし、今まで借入をしていてその返済をしていただけなのに、借金が貯金にかわるかもしれない…といわれても眉唾ものと感じる方も多いかもしれません。

このページでは、過払い金とはどのような権利なのか、実際に事務員として携わっていた経験と、お伝程度法律事務所のスタンスも踏まえてお話しさせていただきます。。
過払い金とは?その仕組みについて知る

まず過払い金とはどのようなものなのでしょうか。
過払い金とは
過払い金とは、消費者金融などが借金を貸し付ける際にする債務者の返済が支払いすぎであったと評価されるため、債務者に返さなければならないお金の事をいいます。
つまり、本来ならば100万円の支払いでよかったはずなのに、120万円の支払いってしまったような場合に、払いすぎた20万円を貸金業者から取り戻そうというものです。
なぜ過払い金が発生するのか
なぜこのような過払い金が発生するのでしょうか。
利息に関する2つの法律がある
消費者金融などの貸金業者はお金の貸付をするときには契約で利息を受け取ることで利益を得ています。
利息も含めて契約の内容は本来当事者が自由に決定できるのが原則なのですが、利息があまりにも高すぎると、お金を借りる債務者が生活できなくなるようなことがあります。
そのため、利息については「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で上限が定められています。
参考:
利息制限法1条
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
出資法5条2項
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

出資法の改正以前には2つの利息は
この出資法については2010年6月18日に改正された出資法が適用されたのですが、それ以前には出資法は29.2%の上限を、そのもっと前には40%を超える利息での貸付容認していました。
一方で利息制限法は制定された昭和29年から現在の利息と変わっていません。
つまり、「(利息制限法=民事)では違法でも、(出資法=刑事)では適法」という利息が存在していたのです(この利息のことをグレーゾーン金利といいます)。
この現象に司法が下した判断は「違法な利息は返しなさい」
この現象に対して、裁判所は次のような判決を出しました。
参考:最高裁判例
昭和39年11月18日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
昭和44年11月25日判決抜粋(本文はこちらから:裁判所ホームページ)
債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。
判決文なので内容が難しいのですが、要は次の3つのことを言っています
- 利息制限法をこえる利息の受け取りは違法
- 受け取った利息は今残っている残額と差し引き計算する
- 差し引き計算をしてもまだ利息の方が多い場合には、貸金業者は利用者に返しなさい
この貸金業者が返すべきとするお金のことが過払い金と呼んでいます。
弁護士や司法書士にとって過払い金の案件とはどのような案件か
法律的な仕組みは以上なのですが、知っておいてほしいのが、弁護士や司法書士がどのようにこの過払い金の案件に取り組んでいるかを知っておきましょう。
実は過払い金を含む債務整理など借金に関する業務については、依頼を受けてからは内部的な事務処理がそのほとんどを占める上に、借金問題については取り扱いたがらない弁護士がかなりいます。

この問題については、事務職員による関わり方を多くして弁護士が関わる工数を減らして業務をまわしていくスタイルで、ビジネスとして成り立たせたことによって取り組む弁護士・司法書士が増えたという経緯があります。
中には仕事をとれなくなった弁護士・司法書士が名義だけを貸してたり、取り戻した過払い金を着服したり、依頼を受けても真面目にとりくまずに案件を放置するなどの問題を起こす人も居ました。

こういった経緯があるので、過払い金を依頼する場合には、債務整理・過払い金請求について真摯に取り組んでいて、かつそれ相応の組織をもっている弁護士・司法書士に依頼するのが適切といえます。
過払い金を返してもらうまでの手続き
過払い金返還請求はどのようにして行うのでしょうか。
弁護士・司法書士に過払い金取り戻しの相談をする
まず、弁護士・司法書士に過払い金取り戻しのための相談をします。
どのような弁護士・司法書士であっても、何らの事前の相談もなしに案件に着手することはありません。
まずは、弁護士・司法書士に事務所に電話で予約をとって、過払い金に関する法律相談の予約をします。

当日は、借金の額やいつから借りていたのかなどについてなどの情報の整理をおこなった上で、過払い金返還請求に関する見通しなどを弁護士・司法書士からもらうことができます。
依頼してみても良いと思える弁護士や司法書士であればそのまま契約してもかまいませんし、他の弁護士・司法書士に相談をしてみることも可能です。
過払い金返還請求を依頼してからの流れ
過払い金返還請求を依頼してからはどのような形で進んでいくのでしょうか。
依頼を受けた弁護士・司法書士は取引履歴を相手方の貸金業者に請求します。
約2週間~2か月程度で貸金業者は取引履歴を弁護士・司法書士に返送します。
弁護士・司法書士は取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法の範囲で借入をしていたならば現在はいくらの過払い金が出ているかの計算を行います(引き直し計算と呼んでいます)。
正確な金額の算出を行った後に、貸金業者と交渉を行います。
この交渉で返還する金額についての合意に至ると、和解契約書を作成した上で、期日に弁護士・司法書士の預り金口座に過払い金を振り込みます。
この金額の中から弁護士・司法書士の報酬を差し引いたものを依頼者に振り込んで手続きは終了となります。
実務上の処理

流れとしては以上なのですが、ここからはより深い内容についてお伝えしようと思います。
過払い金は全額返してもらえない
まず、前提として知っておいていただきたいのが、計算上発生している過払い金は全額返ってくるわけではないという事です。
たとえば、法律上過払い金として、123万1,234円の過払い金が計算上は発生していたとします。
この場合、法律上の請求権の内容としては123万1,234円の元金と、民法の規定に基づいて請求できるようになった日から年五分の利息を請求できることになっております。
参考:民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。


まず、法律上は利息も請求できるのですが、現在はこの民事法定利率の金額まで込みで和解してほしいという提案をすると、断られます。
日本の法律上相手に無理やりにでも払わせるということになると、裁判をした上で判決を取り、相手の財産を強制執行するということになるのですが、それには多大な苦労が伴いますので、現実にこのような方法で過払い金請求をすることはありません。
そして、元金を返還するという話合いになるのですが、元金を100%返還しますという会社も現在では無く、多いところで9割少ないところだと3割を切るような返還提案をしてくる会社があります。
さらに、細かい事ではあるのですが、その割引した元金の端数は、ほぼ下4桁以下はカットというお願いまでされます。

もし、その金額に納得がいかない場合には、裁判を起こします。
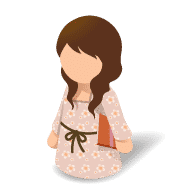

裁判をするということは、勝訴判決をもらうのが目的と思うかもしれませんが、貸金業者内部の処理として裁判を起こした債権については和解できる金額やパーセンテージを引き上げることができることになっています。
裁判を起こすことによって、相手の貸金業者からどれくらいの提案があるかを確認するのが一般的です。

返還されてくるお金からは弁護士費用が引かれます。
まれに、弁護士費用は後から分割で払うから、いったん過払い金は全額返して欲しいという主張をする方もいらっしゃるのですが、本来であれば先に着手金などのお金を払った上で動いてくれるのが弁護士であり、取り戻した額から差し引くのはサービスでやっていることであるという認識があります。
報酬は必ず引かれると考えておきましょう。
計算よりも大幅に少なくなる「争点」がある場合
過払い金の計算で出た金額は弁護士が主張する金額であって、その金額について貸金業者としては法律上の主張をして争ってくることがあります。
このような争うポイントの事を「争点」と呼んでおり、過払い金請求について争点があるような時には過払い金の額が大幅に減少することがあります。
典型的な争点は借入「一連」の借入といえるか「分断」しているかです。
これは、借入をしていたものを一度完済して、その後また借入を再開したような場合に発生します。
この完済してから次の借入までの期間が1年以上開いているような場合には、基本的には取引が2つに分断されると評価されるのが裁判例の傾向です。
たとえば、平成元年から平成25年から借入をして完済したとして、平成10年くらいに一度完済をしていたような場合に、完済をしてから次の借り入れをしたような場合を検討しましょう。
取引の中断期間が1年未満である場合には、平成元年から平成25年までずっと取引が継続していたと評価され、弁護士が計算したシート通りの計算結果になるでしょう。
しかし取引の中断期間が1年以上開いているような場合には、平成元年~平成10年までの取引が第一取引、再度借入をしてから平成25年までの取引が第二取引と評価されます。
このときに、第一取引が原因で発生していた過払い金は平成10年に完済してから、令和元年の今日だとすでに19年経過をしている計算になります。
過払い金請求をする権利の基礎である不当利得返還請求権については、10年の消滅時効にかかることが民法で規定されており、第一取引に基づく過払い金は請求しても認めてもらえません。
つまり、分断の主張が通るケースならば、計算結果出た金額よりも大幅に下がることが予想されます。

まとめ
このページでは、過払い金請求とはどのようなものかを、実務的な細かい話も交えながらお話しさせていただきました。
出資法の改正もあって、過払い金請求は現在では相当前から長期間借入をしていたような場合でなければ発生しないのですが、変換についても困難な問題が伴う請求です。
弁護士・司法書士といった法律専門家に依頼して、あまり大きな期待をせずに取り戻しをする…というような感覚が良いのかもしれません。