目次
不動産の相続をした場合には、相続人は不動産の相続をしたことに基づく名義書きかけをします。
不動産の名義は「登記」で管理されることとなっており、相続を原因とする登記のことを「相続登記」と呼んでいます。
その手続きをするにあたっては書面を提出して行うことになるのですが、どのような書類が必要になるのでしょうか。
このページでは不動産の相続登記の方法についてお伝えします。
登記手続きについて

前提として、登記とはどのようなものか確認しておきましょう。
日本の法律ではある物を持っている場合には、物を自由にする権利があり、その権利のことを所有権と呼んでいます。
所有権を持っている人は、基本的にその物を使ったり、貸したり、譲渡したり、処分したりすることは自由に行うことができます。
当然、自分の所有物について人が使っているような場合には、「それは私のものだから使わないでください」と主張することもできます。
その時に「自分のものです」という主張を裏付けるために、民法所定の「対抗要件」というものを備えていなければなりません。
不動産についての「対抗要件」は民法が規定をしており、「登記」をしていなければならないとしています。
参考:民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
売買当事者が所有権を手にいれたとしても、そのことを第三者に主張するためには上記のように登記をしていなければならなず、売主に登記が残っている場合には他の買主に譲渡してしまい登記をその第三者に移転してしまったような場合には、もはや所有者としての主張ができなくなってしまうのです。
そのため通常の不動産の売買で所有権を移転する場合には、不動産登記をすることになっています。
相続登記とは

相続登記とは、相続を原因とした所有権移転の登記のことをいいます。
相続とは
相続とは、亡くなった人の財産を受け継ぐこと一般をいいます。
所有権を持てるのは「人」であり、人であるためには生きていなければならないとするのが法律の建前で、亡くなった人には所有権は認められません。
その時に亡くなった人が持っていた財産がどのようになるかを民法の相続に関する規定において規律しています。
法律に書いているというと難しいように思うかもしれませんが、配偶者や子、いない場合には親・兄弟というような内容になっています。
法律の規定にしたがって遺産を誰に分配するかを決める協議を行い(遺産分割協議)、所有権を確定させます。
相続登記とは
相続登記とは、相続を原因として発生した所有権の移転についての登記をすることをいいます。
上記のように不動産について相続が発生した場合には、法定相続分での登記をするか、遺産分割協議の結果を反映した登記をします。
この登記をしなければ、従来通り被相続人の名義になっており、現所有者として主張するにあたってたとえ相続人であることが明らかでも「対抗」はできないということになるのです。

相続については各種手続きに期限があります。
相続放棄なら相続開始から3ヶ月、準確定申告は相続開始から4ヶ月、相続税申告は相続開始から10ヶ月、などが代表的なものです。
ところが相続登記については期限がありません。
これは、原因が何であれ所有権の移転の登記は、法律上の義務ではなく、やならなかったら権利者が損をすることがあるだけであるという制度に基づきます。
所有権移転の場合は二重譲渡などの危険があるのですが、相続登記の場合にはそのような危険が遺産分割協議をした後以外は相対的に低いといえ、特に誰も欲しがらないような田舎の荒れ地などは、放置されてしまっているようなケースは散見されます。

この相続登記ですが、法律的な手続きであり専門家に任せる際には、弁護士か司法書士に依頼をすることになります。
しかし、必ず弁護士・司法書士に任せなければならないというものではなく、自分達で行うこともできます。
次の項目以降、自分で相続登記の手続きをするための仕方についてお伝えします。
相続登記をするには
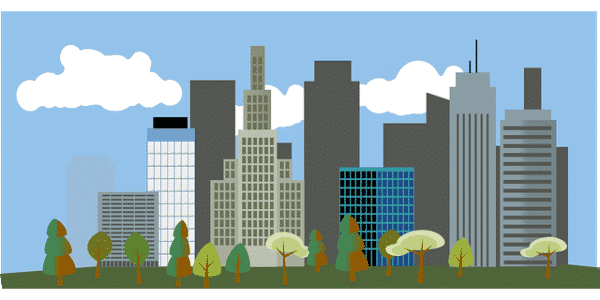
登記をするには、法務局に登記申請書と添付書類を提出して行うことになっています。
法務局とは
法務局とは法務省の事務を扱っている施設で、登記もこちらでおこなっています。
参考:不動産登記法6条
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
法務局といっても法務局から出張所という単位のものまでが全国にあるのですが、基本的には土地が所在する法務局(支局・出張所)に申し込みをして行うことになっています。
どこの法務局がどの不動産を管轄しているかについては、下記の法務局のホームページから確認することができます。
相続登記申請書を作成する
相続登記申請書の作成はどのようにして行うのでしょうか。
記載にあたっては、特にこの様式でないといけない、ということはないのですが、通常は下記の法務局のホームページにあるサンプルを参考にします
たとえば、相続する人全員が不動産を利用しないので、空き家になってしまっているような場合には、遺産分割協議をする前に不動産を一旦共有のまま相続してそのまま売却して、分けやすいお金に変えてしまうということはよくあります。
そのような場合には、法定相続に基づいた相続登記をすることになります。
まずは、サンプルはこのようになっています。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和 元年 5月 1日相続
相 続 人 (被相続人 真似山 一郎 )
東京都◯◯区◯◯町1丁目2番3号
持分2分の1 真似山 花子
東京都◯◯区◯◯町1丁目2番3号
持分4分の1 真似山 一男
神奈川県◯◯市◯◯町2丁目2番3号
持分4分の1 真似 長子
連絡先の電話番号 123 - 456 - 7890
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
令和元年6月1日申請 東 京 法 務 局 御中
課税価格 金 10,000,000 円
登録免許税 金 40,000 円
不動産の表示
不動産番号
所 在
地 番
地 目
地 積
不動産番号
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
文書の表題は書式のとおり「登記申請書」という表記でよく、特に変更の必要はありません。
webでは左寄りになっていますが、実際にwordなどで整える際には中央揃えにすると見栄えが良いでしょう。
登記の目的の項目についても「所有権移転」で大丈夫です。
登記の原因については、相続が発生した日付「相続」と記載します。
相続の発生した日とは、民法で被相続人が死亡した日とされていますので、後述する住民票の除票の亡くなった日と一致させるようにします。
参考:民法882条
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
相続人の欄には、今回の相続の当事者と、それぞれの相続の持分を記載します。
被相続人というのは亡くなった方の氏名を記載します。
相続人の部分には住所・持分・氏名と記載します。
持分については法定相続分の記載をします。
相続人等についてはこちらの記載を参考にしてください。
上記では、被相続人に妻・子が2人という相続が発生したとして記載をしました。
添付情報は「登記原因証明情報」「住所証明情報」の2種類の記載のみでかまいません。
後述する通り戸籍謄本や住民票などを集めますが、これらがすべて登記原因である相続を証明する情報となります。
「□登記識別情報の通知を希望しません。」はそのままにしておいてください。
ここの□にチェックをいれると、登記をした後に登記識別情報というものがもらえません。
ひと昔前ですと登記済証というものが手渡され、それがそのまま「権利書」という言い方をされたのですが、たとえば相続人がそのあと第三者に不動産を売却する際に登記識別情報が必要になります(なくても別の手続きによって登記自体は行えますが非常に面倒です)。
次に法務局に提出する日付と提出先を記載します。
作成段階でいつ行くかわからないような場合には日付を空欄にしておいて後で手書きで書き足してもかまいません。
法務局は上記の管轄を調べて提出先を記載します。
課税価格というのは、登録免許税の計算のためのベースになる価格です。
この価格については、固定資産税の支払いをするために役所から来ている通知に記載されている金額の1,000円未満を切捨てた数字を記載します。
登録免許税は、課税価格に4/1000を乗じた価格になっています。
不動産の表示については、該当する不動産の不動産登記簿に記載のある事項をそのまま記載することになっています。
添付書類をそろえる
上記の書類を作成すれば添付書類を収集します。
添付書類については上記の法務局のホームページにも案内があるのですが、少しわかりづらいためわかりやすくお伝えします。
住所証明情報は住民票を添付する
登記申請書に「住所証明情報」の添付をすると記載したのですが、具体的などのようなものを提出するのでしょうか。
具体的に提出するものは、相続人の住民票を提出します。
住民票はそれぞれの相続人が住んでいる市区町村の市民課で手に入れます。
登記原因証明情報は住民票の除票と戸籍に関する書面
登記原因証明情報については「住民票の除票」と戸籍に関する各種書類を取り寄せます。
この登記の原因は相続で、相続が発生したことと、申請人が相続人であることを証明する必要があります。
まず、相続の発生は被相続人が死亡したら発生するとされているため、被相続人が死亡したことを証明する書類を提出します。
ある人が死亡すると通常医師から死亡診断書が交付され、その死亡診断書を7日以内に市区町村に提出することになっています。
参考:戸籍法86条
第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
この届出に対応して、住民票を消すのではなく、死亡したという記載をすることになっており、死亡した記載がある住民票のことを「住民票の除票」と呼んでいます。
これを提出することで、被相続人が死亡したと判断することができるようになります。
次に戸籍に関する書類を集めます。
戸籍に関する書類を収集することで、申請人と被相続人の間に相続が発生するという関係を証明するのと、法定相続の時は相続分があっているのかを確認するために行います。
上記の申請書の例で言うと、子は2人だと思っていても戸籍を辿ると認知をされた形跡がある場合には、子は3人ということになり、申請書は法定相続分に従った相続分ではない、ということになるのです。
戸籍に関する書類には次のような書類があります。
戸籍事項全部証明書:戸籍を記載したもの
戸籍謄本:戸籍事項全部証明書の昔の形式のもので、実務上は戸籍謄本という言い方をした場合でも現在は戸籍事項全部証明書を取得すれば良い
除籍謄本:戸籍が移転したなどで存在しなくなった時の記録として残っているものが除籍謄本
改正原戸籍謄本:戸籍法の改正により戸籍が新しくなったときに以前の戸籍のことを改正原戸籍と呼んでいます。
戸籍は、出生した際に両親の戸籍に入っており、結婚をすると両親の戸籍を抜けて新しい戸籍がつくられ、子が生まれると自分の戸籍に子が増え、子が結婚すると戸籍から子が抜ける…という風に常に変動します。
基本的には被相続人と相続人の関係を証明し、さらに他に相続人は居ないという戸籍が連続していることが必要になるので、誰が相続人になるかによって必要な戸籍の範囲が異なります。
例えば、子の場合には、親の出生(少なくとも10歳くらいから)死亡までの戸籍と本人が結婚している場合には本人の戸籍が必要です。
兄弟が相続人である場合には、兄弟が相続人になっているケースでは子などの直系卑属・親などの直系尊属といわれる方が不在であることが条件なので、被相続人の生まれてから死ぬまでの間の戸籍と、親の戸籍、本人の戸籍が必要になります。
戸籍の取得については、戸籍がある市区町村の市役所の市民課といった戸籍に関する書類を受け付けているところに申請をすることになっており、場合によっては遠方での取得をしなければならないことがあります。
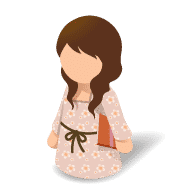

昔の戸籍になると記載が達筆で用意に判読するのが難しい場合があるので、上記のような処理をしてみてください。
相続登記の申請
相続登記の申請書を作成し、添付書類を収集すれば、法務局に提出することになります。
法務局に提出する時には、登録免許税の支払いをしなければならないのですが、これについては収入印紙をはりつける方法で行うのが一般的です。
ですので、法務局には収入印紙を取り扱っている窓口があるので、そちらで事前に登録免許税相当額の収入印紙を購入します。
法務局では登記については、不動産登記と商業登記の2種類の登記を扱っておりますので、相続登記は不動産登記の窓口で行います。
まとめ
このページでは、相続登記をするためのやり方についてお伝えしてきました。
申請書の作成はそんなに難しいものではなく、実は一番難しい(というか面倒)なのは戸籍の収集だったりします。
何のために必要なのか?という事を知っていただいたと思うので、改製原戸籍謄本・除籍謄本など種類に気を付けながら、漏れが無いように戸籍書類を収集し、効率よく相続登記の申請をするようにしましょう。

