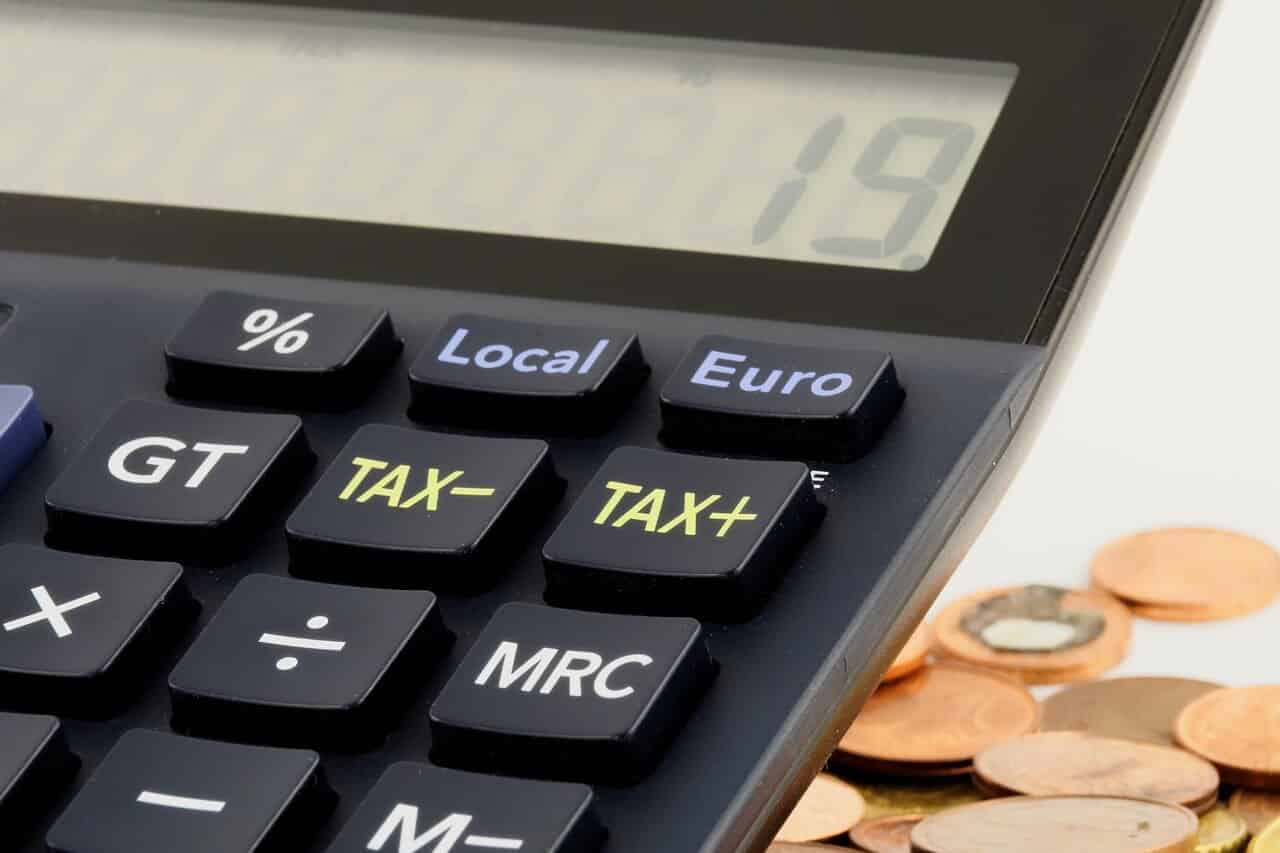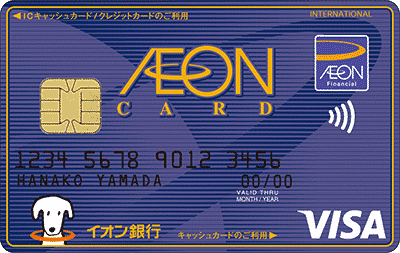目次
亡くなった方が借金をしていて、自分達に請求が来るようになった時に、相続が原因で自己破産をしなければいけないというような事態に納得がいくわけはありません。
そのような事態などを想定して、法律では「相続放棄」という手続きがあります。

このページでは相続放棄を自分で行う方法についてお伝えします。
相続放棄って何か

まず相続放棄とはどのようなものなのかを知りましょう。
親の借金を子が払う必要はない
まず大前提で、当然のことといえば当然なのですが、親が借金をしている場合に子が払う必要はないということは、法律上どう説明されるかを知っておいてください。
借金をするということは、法律上は「金銭消費貸借契約」というものを結ぶことになっており、この契約に基づいて借入をした人は貸付をしてくれた人に返済する義務(貸した側からは「債権」・借りた側からは「債務」という言い方をします)が発生します。
この債務を負担しなければならないのは当然借入をした本人なのであって、その他の人がその支払いをしなければならないという法律は特殊な場合を除いてはありません。

参考:民法761条
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
なお、借金について連帯保証人になっていた場合には請求を受けることがありますが、これは連帯保証契約に基づくもので、他人の債務の請求をされているのではなく、自分の債務の請求をされていると理解しましょう。
借金も相続の対象になっている
その借金ですが、実はマイナスの財産として相続の対象になります。
相続は親の資産を形見分けするということを連想される方も多いと思いますが、法律上は親がもっていた法律上の地位が相続人全員にうつるという内容のものになっています。
家や土地・預金などを持っていた場合には、家・土地の所有者としての法律上の地位・銀行に対する預金債権の債権者としての地位がそのまま相続人にうつるのです。
当然プラスのものがうつるのもあれば、マイナスのものも移ることになります。
その結果、親がした借金が相続をきっかけに「自分の借金になる」ことによって、事実上は親の借金の請求対象になることはあるのです。
相続放棄が活躍する場面
借金負っているような場合であっても自己破産という手続きがあるので、それで良いではないかと思うかもしれませんが、自己破産手続きには信用情報機関への登録がされてクレジットカードを持つことができなくなるなどの様々なデメリットがあり、自分で借金をしたわけではない人が自己破産手続きを利用させられることは納得できない人も多いでしょう。
また、難しい話にはなるのですが、自己破産手続きのもともとの目的は、残り財産が少なくなってしまった債務者の財産を債権者でどう分配するか?ということが主目的で、債務者を免責するのは手続きに参加する見返りとして与えれる「おまけ」でしかありません。
そこで、相続を機に過酷な債務負担をさせられることがないように規定されたのが相続放棄というものです。

相続放棄についての規定を見る
ではその相続放棄はどのようなものなのか、ということを法律の条文とともに紐解きましょう。
どのような理屈で借金の相続をしなくてよいのかについては、この条文が参考になります。
民法939条
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続においては被相続人(亡くなった方)との親族関係に応じて相続人が決定されます。
相続放棄をすることによって、自分は相続人ではなかったという状態にすることができる、とされています。
つまり相続人ではなかったので、借金を相続することもない、という事になります。
相続放棄の手続きを専門家に依頼すると

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に書類を書いて・添付書類をつけて申し込みをすることになっています。
参考:民法936条
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
裁判所に提出する書類なので、専門家に依頼をするという事を検討することになるのですが、どのような専門家に依頼をしてどういった費用がかかるのでしょうか。
まず相続放棄の手続きは、弁護士法72条に規定する「法律事務」となるので、報酬を受けて相談・手続き代行ができるのは弁護士・と司法書士ということになっています。

参考:弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
三 第七十二条の規定に違反した者
参考:司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
弁護士・司法書士に依頼するには次のような費用がかかります。
- 相談料:いきなり相続放棄の依頼をうけるという弁護士・司法書士はいないので、まずは法律相談をすることになるのですが、法律相談については30分5,000円程度の費用が発生します。
- 着手金:弁護士・司法書士は事件に着手をするだけで報酬を受け取ることができることになっており、その費用のことを着手金とよんでいます。
- 成功報酬:相続放棄が終わったときに報酬をもらえるようになっています。
相続放棄に関しては債務整理手続きの一環としてメニューにしている法律事務所・司法書士事務所も多いので、相談料は無料で行うところも多く、手続き自体も安いところだと3万~たかくても10万円程度で手続きに応じていることがほとんどです。
しかし、実際は相続放棄の手続きは、弁護士・司法書士に「依頼します」で終わりなのではなく、裁判所への申告書類をつくるための事情の説明や、裁判所からの問い合わせ対応などが発生します。

自分でやる相続放棄手続き

では、相続放棄の手続きについて解説します。
相続放棄をするためにはまず家庭裁判所に対する申し込みをしなければならないということを念頭に置き、「書類の作成」と「添付書類の収集」を行うことから始めます。
相続放棄の申し込み書類の作成
まずは相続放棄の申し込み書類(相続放棄の申述書)の作成をします。
相続放棄の申し込み書類は、ワープロで作ってもよいのですが、一般的には裁判所に用意されている申し込み書類を利用します。
申し込み書類の取得方法は、担当することになる家庭裁判所に電話で連絡をして書類を郵送してもらうか、下記の家庭裁判所のホームページから取得します。
どこの家庭裁判所が担当になるかというと、亡くなった方の最後の住所地を担当している家庭裁判所が担当することになっています。
参考:家事審判法
第二百一条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
記載内容としては
相続人・被相続人に関する氏名・住所などの記載は添付する住民票どおりに行います。
申述の趣旨のところは印字されたままの「相続を放棄する」という内容で大丈夫で、加筆などの必要はありません。
「相続の開始」は被相続人が亡くなったのを知った日ですので、臨終に立ち会っているような場合やすぐに知らせをもらったような場合には当日としておけばよいでしょう。
相続放棄の理由としては、借金があるような場合には「債務超過のため」に丸をつけておけばよく、相続争いに巻き込まれたくない場合には「その他」に◯をしてその旨を記載するか、「生活が安定している」に◯をつけておけば大丈夫です。
相続財産については概要でかまわないので記載します。
添付書類をあつめる
次に相続放棄に関する添付書類を集めることになります。
添付書類で特に重要になるのは住民票と戸籍関係書類です。
住民票除票
住民票は、被相続人の住民票の「除票」というものを収集します。
亡くなった人に住民票なんかあるのか?という疑問を持つかたもいらっしゃるかもしれませんが、亡くなった人については住民票を消すのではなく、亡くなったという記載をした住民票が作成され(除票といいます)、それを取得します。
この書類が必要とされる趣旨は、被相続人が本当に亡くなっていて相続が発生していることを確認するものです。

取得は市区町村の住民課で行います。
郵送で取得するときは、ホームページで申請書を取得して、返信用封筒と定額小為替というものを利用して料金を納付して行います。
戸籍
次に戸籍に関する書類を収集します。
裁判所のホームページには、実に様々な種類の戸籍に関する書類が必要であるような記載がされています。
これだけを見ると非常に難しいものに思えるのですが、これらの書類が必要な理由は、「被相続人」と「相続人」の関係があるということを戸籍謄本で示すことが目的になっています。
つまり、
- 今回の相続でどういう相続が発生したのか
- 自分が発生した相続で相続人である
ということを証明する戸籍をあつめれば正解となります。
「今回の相続でどういう相続が発生したのか」というのは、民法所定の相続に関する規定のどれにあたるかです。
民法の規定では、
配偶者は常に相続人になるとして
第一順位の相続:子がいる場合には子
第二順位の相続:子がいない場合には親
第三順位の相続:子も親もいない場合には兄弟姉妹
としており、自分が上記のどれにあたるかで収集する戸籍がかわってくるということになります。
自分が子である場合には、親が生まれてから死ぬまでの戸籍と自分が親のところに生まれてきた戸籍のみで良いのですが、自分が兄弟である場合には、被相続人に子が居ない・親が居ないということを確定させるための戸籍を全部収集することになります。
申立
書類の作成が終わって戸籍関係書類が収集されると申立を行います。
作成した書類を持っていく・もしくは郵送で送ります。
申立書に必要な金額の収入印紙を貼付し、郵便切手を指定された枚数揃えて同封する必要があるので注意しましょう。
いくらの郵便切手が何枚必要かは家庭裁判所によって異なるため、事前に家庭裁判所に問い合わせをしておきましょう。
裁判所からの問い合わせ
申立をした後は裁判所のほうで審理にはいります。
裁判所から通知で相続放棄に関する問い合わせがくるので、その内容に返答することになります。
返答内容はどうして相続放棄をしたのか、財産の隠匿や売却などをしていないか、といった常識的なことにとどまるので、あまり気負う必要はありません。
裁判所で審理の上で書類が送られてくる
裁判所からの通知に返答をすると、裁判所がその内容をもとに審理して、財産隠匿や売却などの相続放棄でやってはいけないことをしていないと判断できれば相続放棄の審判をします。
裁判所からは「相続放棄申述受理通知書」が発行されてきますので、請求をしてくる債権者にコピーをして送付すれば、請求はこなくなるようになっています。
3ヶ月を過ぎている場合には専門家に相談
以上は通常の手続きですが、相続放棄に関しては3ヶ月という期間制限があり、3ヶ月を過ぎているような場合には裁判所になぜ3ヶ月を過ぎたのかを合理的に説明できないと相続放棄ができなくなります。
この場合手続きとしても上申書というもので3ヶ月を過ぎた理由の提出が必要になります。
そのため、相続・債務整理に関する専門家である弁護士・司法書士に依頼をするのが良いといえます。
まとめ
このページでは相続放棄を自分でするために必要な知識についてお伝えしてきました。
決して難しい手続きではないので、慎重に行えば自分でできてしまいますので、このページを参考に手続きをすすめるようにしてください。