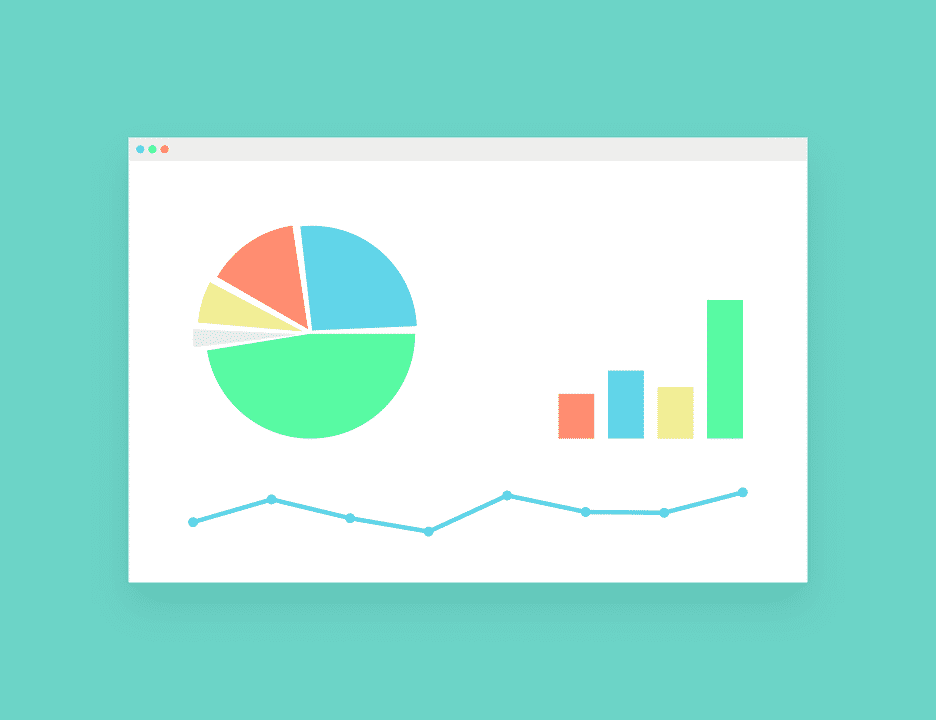目次
債務整理の方法として、借金の返済を免除してくれることによって、経済的な再生が一番早くなる自己破産手続きの利用を検討されている方も多いと思います。
しかし、借金などの債務は返済するのが当然なのが一番の原則論なので、自己破産手続きを利用できる場合も制限されており、利用をするためには条件を満たす必要があります。
このページでは自己破産手続きを利用するための条件についてお伝えします。
自己破産手続きがなぜあるのか

まずは、自己破産手続きがなぜあるのかを知っておいてください。
借金をするということは、法律上金銭消費貸借契約を結んで、金銭を受け取るかわりに、一定の条件のもとに受け取った金銭を利息をつけて返済するという「債務」を負います。
借金以外にも、事業で発生した支払いができなくなったり、他の連帯保証債務の履行を求めれらるなどで、債務は発生します。
法律上債務は必ず払わなければならないのは建前ですが、個人の場合には病気や怪我で仕事ができなくなったり、事業をやっている場合には売上が落ち込んだりするなどして、債務の履行ができなくなる事態は当然に考えられます。
そのような状態に至ってもなお債務は必ず履行しなさいということになると、次の3つの不都合な事態が発生します。
一つ目は、債務者の残りすくない財産をめぐって、本来平等であるべき債権者同士でだれが先に回収するかという争いになってしまい、強引な債権回収方法を行うような事態を招きかねないということです。
二つ目は、たとえば債権者の中に身内がいるような場合には、身内に対する返済を最優先にしてしまうといったように、一部の債権者と債務者が通謀したりするようなことが発生しかねません。
三つ目は、上記のような事態がないにしても、将来を悲観した債務者が犯罪や自殺に走ってしまうような事態も発生しかねません。
自己破産というつくることで、債権者側からみたら、債権の平等な回収が可能になり、債務者としても債務を免れるという結果になることになります。これが自己破産手続きが設けられている理由です。
このことは、破産法1条に破産法の目的として次のように規定されています。

自己破産手続きの条件
自己破産は、債務整理手続きの中でも、債務を原則として帳消しにしてくれる強力な手続きです。
経済的な再生をするために便利な手続きではある一方、安易に債務の支払いから解放するようなものであってはなりません。
そのため、自己破産手続きをするにあたっては、手続きに適した条件を満たしている必要があります。
自己破産手続きの条件である「支払不能」
破産法15条1項の規定を見てください
この条文が何をいいたいかをまとめると
- 債務者が「支払不能」になったら、自己破産手続きを開始する
- 自己破産手続きは、申立てにより開始する
- 自己破産手続きは、裁判所が決定で開始する
自己破産手続きを始めるためには、「支払不能」という状態になることが必要であるとされています。
支払不能というのがどのような状態かは、同じく破産法3条11号が規定をしており、
という事になっています。
この条文から読み解けるのは
- 支払能力を欠いていること
- 債務のうち弁済期にあるものを一般的かつ継続的に弁済することができない
という状態であることが必要とされています。
難しい法律上の規定のお話しをしてきましたので、すこしわかりやすい例をお伝えします。
支払能力がないといえない例
【事例1】
Aさんは家計を完全に専業主婦である妻が握っていてお小遣い制であるため、お小遣いで足りないときに家族に内緒で借入をして賄っていました。家計としては月に15万程度の貯金はできている状態ですが、Aさんの返済額は月10万円をこえることになり、Aさんの小遣いの範囲では返済できなくなってしまいました。Aさんは自己破産して債務を0にできるでしょうか。
このケースでは、Aさんは家族に内緒でしている借り入れの返済が難しくなっていますが、家計としては月15万円の貯金ができている状況です。
このようなときに貯金ができているAさんに自己破産を認めてあげてください、というのは「経済的な再生」という破産法の趣旨とは異なる状態ですね。
つまり、返済能力がないとはいえないので、自己破産手続きは利用できない、ということになります。

一般的かつ継続的に弁済することができないとはいえない事例
「一般的かつ継続的」という法律用語が難しく感じる方も多いかもしれませんが、簡単にお伝えすると「一時的な支払いができない状態」だけでは破産できないということです。
【事例】
Bさんは、会社に勤務していますが、体調を崩し1ヶ月の入院が必要となりました。もともと毎月の給料でギリギリ暮らしており、こんかいの体調不良では一切の公費がおりず、有給等もない状態でしたので、1ヶ月返済ができませんでした。Bさんは翌月からは返済できる状態にはなりました。Bさんは自己破産手続きを利用できるでしょうか。
この場合、Bさんは入院期間中は収入がなく、その次の月の給与支払いに合わせた返済は一時的できなくなっています。
とはいえ、翌月からは返済ができる状態になっているので、収支のバランス次第ですが一瞬返済ができなくなったからといって、安易に破産を認めるのは少し違うといえます。
そのため、一時的にではない状態のことを、法律的に穴の無いように「一般的かつ継続的に」という表現で表しているのであって、上記の事例2のような案件では支払不能とはいえないといえます。
支払不能といえるかどうかの判断基準を実務ではどのように判断するか
では実際に「支払不能」といえるかどうかを実務ではどのようにして判断しているのでしょうか。
「債務の返済が苦しい」といえる場合に債務者に起きていることというと
- 債務の額大きくなっているため毎月の返済額が増えた
- 収入がなくなってしまった・少なくなってしまった
のどちらか、もしくは両方です。
たとえば、毎月の返済額が10万円支払える方でも、月々の返済が8万から12万にふえれば支払いはできなくなるといえます。
また、月々8万の支払いをしている人が、毎月10万のしはらいができていた方が、残業代やボーナスの見込みがなくなり、毎月6万の支払いしかできなくなった場合には支払い不能であるといえます。
つまり、債務額と月々の支払い可能額のバランスで考えることになります。

そして、自己破産をしないで毎月払っていく任意整理をする場合には、総債務額を36回分割で返済できることが基本的な条件になり、36回以上の分割は貸金業者が同意しない可能性がでてきます。
たとえば、180万の債務がある方については、36回の分割にすると月5万円程度の支払いをしなればなりません。
月々に返済可能な金額が月5万円以上ない場合には、任意整理で和解契約を結んでもらったとしても返済できる状態ではないことから、36回の分割で支払いができない場合には間違いなく「支払不能」であると考えて差し支えありません。

その他の条件
自己破産手続きを利用するには支払不能であるだけではだめで、他にも条件を満たす必要があります。
破産法の趣旨である、経済的な再生を許容するには、再生すべきであるとすべての人が容認できるようなものでなければなりません。
しかし、競馬やパチンコなどギャンブルで使いすぎました、キャバクラや風俗などの遊興に使いすぎました、という原因で借金をした人が経済的な再生をしたいです、と言っても容認できないのは容易に想像がつきます。
そこで、破産法は252条でこのような事をしていれば免責しません、というものを列挙しており、法律上は「免責不許可事由」と呼ばれています。

以下条文の中で、一般の方が注意すべき点について言及します。
財産の隠匿
破産手続きは債権者に対する平等な弁済をおこないます。
その債権者に対する平等な弁済の出どころは、当然ながら債務者の今ある個人財産です。
破産手続きをしても生活必需品や一定程度の現金は持っておくことは許されるのですが、もっとく事が許される財産も含めてきちんと申告をしなければなりません。
当然ながらこれを隠匿して債務だけ破産して免責してください、といっても誰も納得するはずはありません。
そのため、免責をしない、という処理が取られます。
借金の原因が浪費や賭博・遊興などである
破産手続きは、日常生活の中でやむを得ずに債務を返済することができなくなった人の経済的な再生を認めようとするものです。
しかし、収支に合わない浪費をしていた、ギャンブルや遊興費で借金をした、というのはある意味自業自得であって、このような人に債権者の財産を犠牲にしてまで債務者を守らなければいけないですか?という事になります。
そのため、m
一部の債権者に対してだけ返済する
借り入れをしている中に、消費者金融や銀行といった個人ではなく、親族や友人・恋人といった人から借り入れをしているようなケースもあります。
そのような場合に、貸金業者は淡々と処理して終わりなのですが、個人からの借り入れを免責してもらって返済しないとなると関係が壊れてしまう、という観点から、個人分だけ返済してしまうというような行動をとる人がいます。
法律上は貸金業者も個人も同じ一人の債権者で平等に取り扱われるべきなので、特定の債権者だけ優遇するような行為は是認できません。
そのため一部の債権者にだけ返済するような行動をすると、免責されなくなります。
破産手続きに関わる人に協力しない
自己破産手続きの申立を行うと、裁判所や管財人といった方の関与を受けます。
これらの人は、法律に則った手続きを進行してくれる人なので、当然に指示があった場合には協力すべきことになります。
このような役割をもった人の破産手続き上の職務を妨害するような行動を取るのであれば、もはや免責を認める必要などありません。
そのため免責をしないとされています。
実際には「裁量免責」によって免責されている

以上のように免責が許可できないという行動をしていたとしても、反省の色がみられるなどで経済的な再生をしてもいい個別の事情はあるはずです。
そのため、裁判官が事情を判断して免責を認めてあげる「裁量免責」という制度があります。
以上の記載の仕方からですと、例外的に認めるような言い方ですが、実際のところギャンブル・遊興による返済困難な債権者も非常に多く、ほとんどのエースで免責自体は認められます。
しかし、この場合には同時廃止という簡単な処理で終わるのではなく、管財人という裁判所から選任される破産手続きを進行していく役割が選任され、免責をするのにふさわしいか調査します。
管財人が選任されるときは、予納金という金銭の支払いが必要となります(東京地裁に申し立てをするときで最低20万円)。
手続き的には負担が増えますが、免責されないわけではないので、あきらめずに弁護士・司法書士に相談するようにしてください。
条件を満たすかどうかの判断は誰がするか

自己破産の条件が満たされているかどうかは、だれがどのように判断するのでしょうか。
破産手続きについては裁判所が「決定」という形で認めることになっており、自己破産の条件を満たしていないとこの「決定」をすることができないので、裁判所が決定をするという形で条件が満たされているという判断をすることになっています。
最終的な判断は裁判官ですが、自己破産をするための条件を満たしていない場合には、弁護士・司法書士は自己破産の手続きの依頼をうけることがないので、弁護士・司法書士も判断をすると考えておきましょう。
まとめ
このページでは自己破産手続きを利用する条件についてお伝えしてきました。
大きくまとめますと「支払不能」にあることと、「免責不許可事由」がないことが条件です。
破産法が何を目指しているのかを知った上で、常識的に考えて経済的再生をすべき場面にある場合に、誠実に手続きをしていれば、条件に合わず自己破産手続きができなくなるという事はありませんので、自分が条件を満たしているかどうかを心配する前に、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。